相続Q&A
A1:正しい。
相続とは、ある人の死亡により、その者の財産に関する権利義務の一切を、その者と一定の身分の関係にある者が引き継ぐことをいいます。
そして、亡くなった人のことを被相続人、被相続人の財産(負債を含む)を相続する権利を持つ人を相続人と呼びます。
さて、被相続人となる人が亡くなりますと、誰が相続するかには関係なく、相続が開始します(民法882条)。
そして、その相続は、被相続人の住所において開始することになります(民法883条)。つまり、相続財産の存在する場所や、被相続人の死亡した場所(病院等)ではないということです。
相続に絡む裁判を起こす場合に、どの場所にある裁判所の管轄になるのかを決めるときに必要となりますので、このように規定されています。
Q2:相続回復請求権の5年の短期消滅時効の起算点は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時である?
A2:正しい。
相続回復請求権とは、相続開始後に相続人が相続することのできる権利を第三者に侵害された場合に、その権利の回復をするように請求できる権利のことをいいます。
そして、相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知ったときから5年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法884条前段)。
これは、いつまでも回復請求権の行使を認めていますと、権利の確定ができない不安定な状態が続いてしまうためです。
ちなみに、相続回復請求権には、この短期消滅時効以外に、相続開始の時から20年を経過したときも、この相続回復請求権は消滅すると規定されています(民法884条後段)。
Q3:先日、私の祖母が亡くなりました。祖父は既に亡くなり、祖母の子供は母のみですが、母は祖母より先に亡くなっています。祖母の相続について教えてください。
A3:この場合、あなたが母に代わって祖母の相続人となります。このような相続を「代襲相続」といいます。
被相続人の子が、以下の原因によって相続権を失ったときは、その者の子が代襲して、相続人となります(民法887条2項)。
| 代襲相続が発生する原因 |
| (1)相続の開始以前に死亡したとき |
| (2)欠格事由に該当するとき |
| (3)廃除されたとき |
今回の場合では、被相続人(祖母)の子(母)が、相続の開始以前に死亡したことを原因として相続権を失ったため、その者(母)の子(あなた)が代襲して、相続人となります。
なお、代襲相続が発生する原因は上記の3つであり、「相続放棄」は代襲相続の原因とはなりません。
代襲者は、被相続人の直系卑属がなります。今回の場合では孫です。
相続人が、配偶者と被相続人の兄弟姉妹である場合において、被相続人の兄弟姉妹が上記の「代襲相続が発生する原因」に該当する場合には、その者の子である甥(おい)、姪(めい)が代襲相続します。
●代襲相続できない者
被相続人の直系尊属は代襲相続することができません(民法887条2項但書)。今回の場合は、亡くなった祖母の直系尊属である父母、祖父母、曾祖父母などです。
●再代襲相続できる者
もし、代襲者自身が「代襲相続が発生する原因」に該当して代襲相続権を失ったならば、さらに代襲相続(再代襲相続)が発生します。孫の代襲者として、曾孫(ひまご)→玄孫(やしゃご)と続きます。
●再代襲相続できない者
民法は、甥(おい)、姪(めい)の子に再代襲相続を認めていません。
●代襲相続の注意点
以上のように、代襲相続は、本来相続すべき相続人が3つの代襲相続が発生する原因のいずれかに該当したときに、その者に代わって代襲者が相続する制度です。
代襲者は、相続人ですから、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純承認もしくは限定承認または相続放棄をしなければなりません(民法915条)。
ところが、代襲相続は、代襲者にとって、身近な相続でないがために、自己が相続人であることを知らず、いつの間にか相続人となってしまい、相続の準備ができなかったという状況に陥ることも考えられます。
例えば、身近な相続でない場合として、本来相続すべき者と代襲者が孫、曾孫、玄孫、甥、姪などの場合です。
したがって、自己に身近でない親族の相続があったときには、自己が代襲者となっているのか否かを確認し、代襲者となっていた場合には、上述の3ヶ月以内に、相続について、承認または放棄を決定する必要があるといえます。
Q4:相続開始時以前に子が死亡しているときは、その者の子は代襲相続権を有しない?
A4:誤り。
被相続人の子(実子、養子)は、相続人となり(民法887条1項)、被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法890条)。
被相続人の子が胎児の場合には、死産となった場合を除き、相続については既に生まれたものとみなされます(民法886条)。
更に、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときや、相続人の欠格事由に該当した場合、若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります(民法887条2項)。これを代襲相続といいます。
そして、代襲相続をする者がいない場合には、被相続人の直系尊属及び兄弟姉妹に相続権が発生します。この場合も、被相続人の配偶者がいれば、その者と一緒に相続人となります。
今回の事例では、本来相続人となるべき被相続人の子が先に死亡し、その死亡した子には子がいますので、この者(今回の被相続人から見ると孫)が、代襲相続をする権利を得ることになります。
Q5:Bは被相続人Aの実子であったが、AとBがいずれも死亡し、両者の死亡の前後が分明でない場合、Bの実子であるCがBを代襲して相続人となることができる?
A5:正しい。
まず、簡単に図示しますと以下の通りです。
被相続人A=死亡
|
子B=死亡
|
子C
相続人となりうる者は、被相続人の死亡時に生存していなければなりません。これを同時存在の原則といいます。
そして、被相続人の死亡時に生存していない場合には、代襲相続の可能性があるだけになります。
さて、この事例では、被相続人と相続人たる子の2人が、ともに死亡しているものの、どちらが先に死亡したのかが不明となっています。
この場合、民法の規定では、同時に死亡したものと推定する(民法32条の2)と規定されています。これを同時死亡の推定といいます。
そして、このような場合には、一方の相続開始時に他方は死亡によって権利能力を失っています。よって、両者の間に相続の問題は生じませんので、相続人の子が代襲相続をすることができるということになります。
Q6:相続について同順位にある者を過失により死に至らしめたため、罰金刑に処せられた者でも、相続人となることができる?
A6:正しい。
本来相続人に該当する者でも、相続人としてふさわしくない何らかの事由がある場合には、法律上、相続権を剥奪され、相続人とならないことがあります。これを「相続欠格」といいます(民法891条)。
民法では、以下の者については、相続人になれないとしています。
(1)故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者(民法891条1項1号)
(2)被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない(民法891条1項2号)。
(3)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者(民法891条1項3号)
(4)詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者(民法891条1項4号)
(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(民法891条1項5号)
この事例で問われているのは、上記の民法891条1項1号についてです。
つまり、民法891条1項1号では被相続人または先順位・同順位にある者に対する殺人罪や殺人未遂罪、殺人予備罪が認められる場合には、相続人としてふさわしくないという理由で欠格者になります。
しかし、この事例では、故意ではなく過失であり、過失致死罪に該当しますので、欠格事由には該当しないということになります。
ちなみに、傷害致死罪の場合も、欠格事由には該当しません。
Q7:詐欺によって、被相続人に対して相続に関する遺言を変更させた者でも、家庭裁判所の審判を経なければ、相続人となる資格を失うことはない?
A7:誤り。
詐欺によって、被相続人に相続に関する遺言を変更させた者た場合には相続欠格に該当します(民法891条1項4号)。
では、相続欠格者から相続権を剥奪するためには、家庭裁判所の審判が必要なのかといいますと、これは不要です。
といいますのは、法律の条文で当然に相続欠格として相続権を剥奪していますので、家庭裁判所の審判を介する必要がないためです。
Q8:被相続人を虐待した者でも、被相続人から廃除されないかぎり、相続人となることができる?
A8:正しい。
被相続人を虐待していますので、社会倫理的に考えれば、相続分を与えるべきではないのかもしれませんが、少なくとも法律上の欠格事由(民法891条)には該当しません。
そこで、被相続人が生前に若しくは遺言で、推定相続人のうちで相続させたくない者に対して相続権を剥奪してしまうのが、「廃除」という制度です。
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます(民法892条)。
この廃除請求が家庭裁判所で認められますと、その者は推定相続人から外れることになります。
ちなみに遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が受け取ることのできる、相続財産の一定の割合(民法1028条)のことをいいます。
つまり、遺留分を持つ相続人については、その者の生活の保証という観点から、相続財産の一定割合を必ず受け取ることができる権利を付与しています。
よって、遺留分を侵害するような遺言や遺贈があっても、遺留分権利者は自己の分を取り返すことができます。しかし、廃除をされてしまいますと、この遺留分についても権利を失うことになります。
Q9:相続欠格の対象となるのは、すべての推定相続人であるが、相続人の廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人のみである?
A9:正しい。
相続欠格の対象者については、民法の条文を見てみますと、全ての推定相続人となっています(民法891条参照)。
一方、廃除の対象者については、遺留分を有する推定相続人のみとなっています(民法892条参照)。
つまり、相続財産をある推定相続人に相続させないようにするためには、その内容の遺言をすればすむのですが、遺言は、遺留分を剥奪することはできませんので、遺留分を有する推定相続人からその遺留分の権利を剥奪するために廃除の制度があるということになります。
Q10:Aには、妻Bと子Cがいて、Aが相続人の1人である妻Bを受取人とする生命保険契約を締結していた場合、その死亡保険金は相続財産に含まれる?
A10:誤り。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。
つまり、相続の対象となるものは、一身専属権を除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務ということになりますが、生命保険金の請求権というものは、本来受取人に帰属する権利ですので、上記の相続財産には該当しないことになります。
よって、Aの死亡保険金は妻Bが全額取得することができ、遺産分割の対象にはならないことになります。
Q11:無権代理の相続とは?
A11:「無権代理」とは、代理権が与えられてないのに、勝手に「自分は○○の代理人だ。」と称して法律行為を行うことです。例えば、子供が父親に無断で、父親の代理人を名乗って、父所有の絵画を売るような場合です。
この場合、父親は、渋々その行為を追認するか、もしくは契約は無効であると追認を拒絶することができます。
そして、もし父親か子供のどちらかが死亡すると相続問題が発生します(親1人子1人のみで、他に法定相続人がいないものとします。)。
まず、父親が死亡した場合、無権代理行為を行った子供が父親を相続します。
相続とは単に財産や負債だけでなく、一切の権利・義務も継承しますから、子供は父親の追認権と追認拒絶権という権利も受け継ぐことになります。
すると、この子供は自分で無権代理行為を行っていながら、同時に父親の権利である追認拒絶権を行使して契約無効を主張できるか? という問題が発生してきます。
民法にはそういう場合に限定した明確な条文はありませんが、判例では、この場合、絵画の所有者である父親本人が売買契約をしたのと同じ法律的地位を生じたものと解して、子供は追認拒絶(契約無効の主張)はできないとしています。
もっとも父親が死亡する前に明確に追認拒絶の意思表示をしていた場合には、いくら相続があっても、その売買契約は無効となります。
次に、子供が親に先立って死亡した場合、父親が子供を相続します。
この場合、父親は追認拒絶(契約無効の主張)ができますが、一方で追認が拒絶された場合に子供が負うべき売買先に対する損害賠償義務も相続しているので、結果的には自分で契約を無効にして、自分でその賠償金を売買先に払わなければなりません。それが嫌なら子供の無権代理行為を追認して、絵画を売り渡すしかありません。
Q12:Aを被相続人とし、Bを唯一の相続人とする相続に関し、Bが権限がないのにAの代理人としてA所有の土地をCに売り渡した後にAが死亡した場合、BはCに対する当該土地の所有権移転登記の申請義務を負わない?
A12:誤り。
この事例におけるBは、代理権を有しない代理人です。これを無権代理人と言い、本人の追認がなければ、この者が行った代理行為は効力を生じません(民法113条2項)。
Aは追認をしていませんので、A-C間の売買は無効のままであり、Bと取引をしたCに対しては、Bが責任を負うことになります。
その後本人たるAが死亡し、Bが唯一の相続人となったことにより、BがAの権利義務を全て承継することになります。
そうしますと、BはAの立場を利用して、Cとの取引を拒絶することも可能だと思われますが、それでは無権代理人として勝手に売買をしたBを不当に保護することになってしまいます。
判例ではこのような場合、BはCとの取引について拒絶することは信義則に反することから認められないとし、Bの無権代理行為については、Bの相続とともに当然に有効になるとしています(最判S37.4.20)。
よって、A-C間の取引は有効となり、BはCに対して所有権移転登記の申請義務を含め、当該土地の引渡し義務を負うことになります。
A13:誤り。
不法行為とは、一方の人の故意・過失により、相手方に損害を与える行為を指します。
そして、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法709条)。
この事例では、AがCに対して何らかの不法行為をし、その結果、Cは精神的苦痛を受けたわけですから、Aには損害賠償責任が発生します(民法710条)。
本来ですと、CはAに対して慰謝料を請求すべきところですが、請求する前にAが死亡してしまったため、Aの唯一の相続人Bに対しても、Cが請求できるかどうかが問題となります。
この点に関しては、判例では、慰謝料請求権は現実に損害が発生したときに生じるものであり、被害者が加害者に対して具体的に請求の意思表示をしたか否かには関わらないとしています。
つまり、Aの損害賠償責任は、現実に損害が発生したときに生じていますので、Bはこの責任も相続することになります。よって、BはCに対して慰謝料の支払義務を負うことになります。
Q14:共同相続人中に被相続人から贈与を受けた者がいるときは、他の相続人は、家庭裁判所の審判によらなければ、その贈与財産の価額を加えたものを相続財産とみなすことができない?
A14:誤り。
相続人は、被相続人の財産(相続財産)を相続する権利があります。その相続財産の範囲として、まず、被相続人が相続開始の時点において有した財産は当然含まれます。その他にも、被相続人が生前に共同相続人いずれかに対して、ある一定の事由による贈与をしていた場合なども、その贈与分を相続財産とみなすこととしています。これをみなし相続財産といいます。
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします(民法903条1項)。
この事例では、共同相続人中に、被相続人から贈与を受けた者がいますので、その贈与の趣旨が上記の条文の内容に合致するものであれば、当該贈与の価額を加えたものを相続財産とみなすことになります。このような贈与や遺贈を特別受益といい、受贈者を特別受益者といいます。
このような特別受益者がいる場合には、家庭裁判所の審判によることなく、当然にその特別受益分を相続分に加えることになります。
Q15:相続分の指定は、遺留分に関する規定に違反している場合であっても、遺留分権利者による減殺請求があるまでは有効である?
A15:正しい。
遺留分とは、一定の範囲の相続人のために、必ず保留しておかなければならない遺産の一定割合(民法1028条参照)をいいます。これは、相続人の生活を守るために定められています。
さて、相続人が被相続人の相続財産を相続するにあたり、民法では、法定相続分(民法900条)というものを定めています。
ただし、この法定相続分は相続人を拘束するものではありませんので、相続人全員で遺産分割協議をして、各々の相続分を定めることができますし、被相続人も、生前に遺言をすることで、法定相続分にとらわれずに、原則として自由に相続分を定めることができます(民法902条1項本文)。これを相続分の指定といいます。
ただし、上記の理由から、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない(民法902条1項但書)としています。
よって、遺留分に関する規定に違反する遺言はできないのですが、もしこのような遺言をしてしまった場合でも、それが当然に無効となる訳ではありません。
このような場合には、遺留分を侵害された者(遺留分権利者)が、自分の遺留分を保全するのに必要な限度で遺留分減殺請求をする(民法1031条)ことで、初めてその侵害部分が失効することになります。
Q16:共同相続人中に相続財産の増加に特別の寄与をした者がいるときでも、家庭裁判所の審判を経なければ、寄与分を控除したものを相続財産とみなすことはできない?
A16:誤り。
民法では、共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする(民法904条の2第1項:寄与分)と規定されています。
この寄与分の制度は、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者に対して、その貢献度にあたる部分の財産を与えることで、共同相続人間の相続財産の分配の公平を図ろうとするものです。
そして、この条文にあるとおり「みなす」規定になっていますので、原則として家庭裁判所の審判は不要です。
ただし、上記の条文の協議が整わないときや、協議をすることができない場合には、寄与分権利者の請求により、家庭裁判所が寄与分を定める(民法904条の2第2項)こともあります。
Q17:被相続人の妻の通常の家事労働も、特別の寄与に該当する?
A17:誤り。
寄与分として認められるのは、あくまでも「特別」の寄与に限られます(民法904条の2第1項)。
つまり、この事例で問われている通常の家事という夫婦間の協力および扶助の義務の履行(民法752条)については、通常の寄与にすぎず、このような通常の寄与については、法定相続分で配慮していることなどから、更なる加算対象にはならないとされています。
Q18:寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることができない?
A18:正しい。
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません(民法904条の2第3項)。
寄与分の制度は、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者に対して、その貢献度にあたる部分の財産を与えることで、共同相続人間の相続財産の分配の公平を図ろうとするものです。
ただし、被相続人の最終意思である遺贈を侵害することは良くないので、遺贈の価額を除いた範囲内で定めることとした訳です。
Q19:被相続人から廃除された者も、被相続人と同居して特別の寄与をしたときは、寄与分を取得することができる?
A19:誤り。
廃除とは、遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときに、被相続人が、その者を推定相続人から除外することを家庭裁判所に請求できる制度です(民法892条)。
よって、被相続人から廃除された者は、相続人としての地位を剥奪されていますので、たとえ被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたとしても、寄与分の取得の対象者とはなりません。
Q20:遺言で一定期間遺産分割が禁じられていても、共同相続人全員が合意すれば、いつでも遺産分割をすることができる?
A20:誤り。
民法では、共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる(民法907条1項)と規定されています。
つまり、原則として共同相続人は、いつでも遺産分割をすることができるのですが、その例外として、被相続人が遺言で一定期間、遺産分割を禁止することができます。
その禁止期間は、相続開始のときから5年を超えない期間内とされています(民法908条)。
よって、たとえ共同相続人全員が合意しても、遺言で分割を禁止された期間(相続開始から5年の範囲内)は、遺産分割をすることはできないことになります。
Q21:被相続人の遺言により遺産の分割を禁止する場合は、全部または特定の遺産についてすることができる?
A21:正しい。
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができます(民法908条)。
この遺言による遺産分割の禁止が認められているのは、被相続人の最終意思を尊重するためです。よって、当該遺産分割禁止の範囲は、遺産の全部でも構いませんし、特定の財産のみでも構わないということになります。
Q22:共同相続人の協議により遺産の分割を禁止した場合において、その禁止期間が経過したときは、共同相続人は直ちに分割しなければならない?
A22:誤り。
民法は、共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる(民法907条1項)と規定されています。つまり、原則として共同相続人は、いつでも遺産分割をすることができます。
その例外として、民法908条の遺言による分割の禁止がありますが、その他にも、共同相続人の全員の協議により、5年を超えない期間において、遺産の分割を禁止する契約をすることができます(共有物の分割禁止特約:民法256条1項但書)。
ただし、その分割禁止期間が経過したからといって直ちに分割しなければならない訳ではなく、その後は原則に戻って、いつでも遺産分割協議ができるようになるだけです。
Q23:共同相続人の協議により遺産の分割を禁止した場合であっても、共同相続人全員の合意があれば、禁止期間内に分割することができる?
A23:正しい。
共同相続人の全員の協議によって、5年を超えない期間内であれば、遺産の分割を禁止する契約をすることができます(民法256条1項但書)。
この合意による遺産分割禁止はあくまでも契約ですので、当事者全員の合意があれば、契約解除をすることが可能です。
遺言による分割禁止期間内は、共同相続人全員の合意があっても分割が認められないという場合と混同しないようにしましょう。
Q24:相続財産に属する不動産につき、共同相続人の1人が法定相続分を超える持分を取得する旨の遺産分割の協議が整ったときは、その相続人は、他の相続人からその持分を譲渡されたことになる?
A24:誤り。
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます(民法909条)。
つまり、遺産分割の行為自体は、相続開始後、ある程度の時間が経ってから行われることになりますが、遺産分割の効果は、相続開始の時、つまり、被相続人の死亡時まで遡及することになります。
この事例のように、遺産分割協議が整った時にその効果が相続開始時点まで遡及しますので、被相続人から各々の相続人が、その協議によって定めた割合を相続したことになります。よって、他の相続人から持分を譲渡されたことにはなりません。
Q25:遺産の分割後に認知によって相続人となった者は、自己がその分割の当事者となっていないことを理由に、遺産の分割の無効を主張することはできない?
A25:正しい。
遺産分割協議は、共同相続人全員でなされなければならず、1人でも参加していない協議は、無効となります。
しかし、この事例のように、遺産分割時点では相続人とはなっておらず、後日認知によって相続人となった場合まで、協議を無効としてしまいますと、いつまでも遺産分割の効果が確定せず、不安定な状況になりかねません。
民法では、相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する(民法910条)と規定しています。
つまり、遺産分割協議自体は有効とし、その代わり、価額による支払の請求権を与えることで、被認知者の金銭的補償を図っています。
Q26:各共同相続人は、遺言による別段の定めがない限り、連帯して、他の共同相続人が遺産分割によって受けた債権について、分割の当時における債務者の資力を担保する?
A26:誤り。
各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保します(民法912条1項)。これを共同相続人の担保責任といいます(民法911条〜民法913条)。
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます(民法909条本文)が、この遺産分割というものは、実際には相続人同士が持っている法定持分のやりとり(交換)といえます。
よって、共同相続人相互間での利益の分配の不公正を是正するために、このような担保責任が定められています。
つまり、遺産分割によって債権を取得した相続人について、もしその後この債権が債務者の資力を原因として回収できない状況に陥った場合には、他の共同相続人は、その相続分に応じて、資力を担保する責任を負うことになります。
この事例では、「連帯」して債務者の資力を担保することとしていますが、条文では「連帯」とはしていませんので、誤りとなります。
Q27:A及びBが共同相続人である場合における遺産分割に関し、AB間においてAのみに相続債務の全額を相続させる旨の遺産分割の協議が調った場合には、債権者は、Bに対して相続債務の履行を請求することができない?
A27:誤り。
判例では、債務者である被相続人の負の財産である債務について、相続人が数人あるときは、金銭債務その他の可分債務は法律上当然に分割され、各共同相続人がその(法定)相続分に応じてこれを継承するとしています。
そして、その後遺産分割協議が行われ、その結果、共同相続人の1人が相続債務の全てを相続することになった場合、もし、その者に財産がなかった場合、債権者としては不利益を被ることになりますので、債権者の同意なくしては認められないことになります。
つまり、このような債務の遺産分割は、いわゆる免責的債務引受と同様のものといえますので、債務者の共同相続人間では有効ですが、債権者に対しては、債権者の同意がない以上は有効とはなりませんので、債権者は遺産分割協議後でも、各共同相続人に対して、法定相続分に応じた債務の履行を請求することができます。
Q28:相続の承認または放棄の3箇月の熟慮期間の起算点は、相続人が被相続人の死亡の事実を知っただけでなく、被相続人の死亡により、自己が相続人となったことを知ったときである?
A28:正しい。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません(民法915条1項本文)。これを熟慮期間といいます。
この条文の文言だけを見ますと、「知ること」のみでもよさそうにも思えますが、判例では、相続人が相続開始の原因である事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知したときであるとしています。
つまり、相続人は、相続を承認するのか放棄をするのかを、原則としてこの3箇月間で決めなさいという趣旨ですから、自分が相続人になったことまでを知覚していなければならないということになります。
ちなみに、熟慮期間には例外があります。つまり、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます(民法915条1項但書)。
A29:正しい。
民法915条1項に定められている熟慮期間について、判例では、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または通常これを認識しうべきときから起算すべきであるとしています。
Q30:相続の開始前でも、家庭裁判所の許可を得れば、相続の放棄をすることができる?
A30:誤り。
相続が開始した後、相続人が取れる選択肢は、相続の承認、限定承認、相続の放棄のいずれかになります。
そして相続人は、この選択を、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内にしなければなりません(民法915条1項本文)。これを熟慮期間といいます。
ただし、この熟慮期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます(民法915条1項但書)。
しかし、相続開始前に相続の承認・放棄をすることは認められず、これは家庭裁判所も関与できません。
その理由は、相続開始前の場合、実際の相続財産がどの程度のものか全く分からず、相続人にとって判断ができないことや、これを認めてしまうと不当な圧力を受けることもありうるためです。
A31:誤り。
簡単に図示すると以下の通りです。
(被)A=B
│
(死亡)C=D
│
E
被相続人Aの死亡時にはCは生存していますので、CはBと共にAの相続人となります。
そして、Cは相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内に、Aの相続の承認または放棄をしなければならないのですが、その期間の経過前に死亡してしまったので、今度はCの相続人Eが、Aの相続の相続・放棄の判断をすることになります。
この場合、民法では、相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときの熟慮期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する(民法916条)と規定しています。
この理由は、E自身に熟慮できる期間を改めて与えないと、Eが相続の承認・放棄の判断をできないという不利益を被る恐れがあるためです。
Q32:相続の放棄をした者は、自己のために相続が開始したことを知った時から3箇月以内であれば、その放棄の撤回をすることができる?
A32:誤り。
相続の承認及び放棄は、民法915条1項の熟慮期間内でも、撤回することができません(民法919条1項)。
これは、相続の承認・放棄は重要な意思決定ですので、これを後日撤回できるとしますと、他の共同相続人や債権者等の利害関係人に不測の損害を与える恐れがあるためです。
Q33:甲が死亡し、その子であるA及びBのために相続が開始した事例において、BがAの詐欺により相続放棄の意思表示をしたときは、Bは、家庭裁判所に申述することによって、その放棄を取消すことができる?
A33:正しい。
原則として相続の承認・放棄の撤回はできません(民法919条1項)が、詐欺・強迫を理由とした取消し等は可能です(民法919条2項)。
限定承認又は相続の放棄の取消しをする場合には、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません(民法919条4項)。
ちなみに、民法919条2項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときまたは、相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときは、時効によって消滅します(民法919条3項)。
Q34:相続人が相続の開始を知らずに被相続人の財産を処分した場合であっても、単純承認をしたものとみなされる?
A34:誤り。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません(民法915条1項本文)。
単純承認とは、正の財産および負の債務についての一切を相続をすることを承認するというものです。
民法では、相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する(民法920条)と規定されています。
この単純承認は、相続人の意思表示が原則ですが、それ以外にも民法では、相続人がある一定の行為をした場合には、単純承認をしたものとみなす(民法921条)と規定しています。これを法定単純承認といい、以下の3つの場合が挙げられています。
1号:相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2号:相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3号:相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
この法定単純承認が定められている理由としては、例えば、相続人が相続財産の処分などといった行為をすれば、他の相続人や相続財産の債権者などは、その者が単純承認をしたものと思いますので、その後に相続放棄などができるとしますと、それらの者に不測の不利益をもたらす可能性があるためです。
では、この事例における財産の処分は、上記の1号に該当するのかといいますと、これは該当しないと判例(最判S42.4.27)は示しています。
つまり、法定単純承認とみなすためには、その相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った上で、または少なくともその事実を確実に予想しながらあえて相続財産の処分をする必要があるためです。
ちなみに上記の条文(民法921条1項2号)で出てきましたように、熟慮期間の3箇月間に限定承認または放棄をしなかった場合には、単純承認とみなされます。つまり、民法では、相続の単純承認が原則であると考えているということになります。
Q35:相続人が火を失して相続財産である建物を焼失した場合であっても、単純承認をしたものとみなされる?
A35:誤り。
相続人が相続財産の全部又は一部を処分する行為は、法定単純承認とみなされます(民法921条1項1号)。
しかし、この処分行為は、あくまでも相続人の処分する意思が必要ですので、この事例のような失火による焼失については、該当しないことになります。
Q36:相続人が相続財産の不法占有者に対し明渡しを求めたときは、単純承認をしたものとみなされる?
A36:誤り。
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなします。
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りではありません(民法921条1項1号)。
この事例における不法占有者に対する明渡請求は、処分行為ではなく、保存行為です。よって法定単純承認には該当しないことになります。
Q37:相続人が相続財産である建物の賃借人に対し賃料の支払いを求めたときは、単純承認をしたものとみなされる?
A37:正しい。
相続人が、相続財産である債権について、これを取り立てて受領する行為は、判例では処分行為とされています。よって、法定単純承認とみなされます。
Q38:甲が相続を放棄したことにより、新たに相続人となった乙が単純承認をした後であっても、甲が相続財産の一部を私に消費したときは、単純承認をしたものとみなされる?
A38:誤り。
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(民法921条1項3号:法定単純承認)。
よって、原則として「私に消費」すれば、たとえ限定承認や放棄をしていたとしても、法定単純承認とみなされることになります。
ただしこの例外として、「私に消費」した相続人が相続の放棄をしたことによって新たに相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りではない(民法921条1項3号但書)と規定しています。
これは、このような場合にまで法定単純承認を認めてしまいますと、次順位者にとっては、相続人の地位を剥奪されてしまうことになり、不測の損害を被ることになるため、この次順位者を保護する必要があるからです。
Q39:共同相続人は、家庭裁判所の許可を得たときは、各別に限定承認をすることができる?
A39:誤り。
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができます(民法922条)。これを限定承認といいます。
限定承認とは、正の相続財産と負の相続財産(債務や遺贈等)のどちらが大きいのかが明らかでない場合に、正の相続財産の限度においてのみ、負の相続財産を相続する(弁済などをする)という条件をつけた相続の承認形態です。
よって、相続人としては、負の相続財産が多かった場合でも、最悪±0で終えることができるというわけです。
この限定承認をする方法は、3箇月間の熟慮期間内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません(民法924条)。
また、相続人が複数存在する場合には、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます(民法923条)。
これは、共同相続人の1人が限定承認をして、他の相続人が単純承認または放棄をするということになりますと、法律的に複雑となり、その後の清算手続も煩雑となるためです。
Q40:債務者が債権者を相続した場合であっても、債務者が限定承認をしたときは、当該債権は混同により消滅しない?
A40:正しい。
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅します(民法520条)。これを、債権の混同による消滅といいます。
しかし、相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなします(民法925条)。
これは、限定承認の場合には、必ずしも当該相続人がこれらの債権債務を相続するかどうかは不明なため、もし消滅させてしまった後に復活するようなことがありますと、債権者・債務者に不測の損害を与えかねないためです。
Q41:限定承認をした相続人は、自己の被相続人に対する債権については、他の債権者が相続財産から全額の弁済を受ける場合に限り、相続財産から弁済を受けることができる?
A41:誤り。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることです(民法922条)。
家庭裁判所に対してこの限定承認をする旨を申述した後、限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内(2箇月以上)にその請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません(民法927条1項)。
そして、この公告期間満了後、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければなりません(民法929条)。これを配当弁済といいます。
さて、限定承認をしますと、相続人の被相続人に対する債権は消滅しなかったものとみなされます(民法925条)ので、相続人も債権者の1人として、この配当弁済に加わることになります。
この場合の相続人の弁済順位は、他の債権者に劣後する訳ではありませんので、債権額の割合に応じて弁済を受けることができます。
Q42:18歳の者は、単独で相続の限定承認をすることができる?
A42:誤り。
婚姻や縁組のような身分行為に関しては、未成年者のような制限行為能力者であっても意思能力があれば良いとされています。
しかし、相続の承認・放棄という行為は、身分行為のうちでも財産に関する行為ですから、通常の行為能力が必要となります。
よって、未成年者が相続人の場合には、法定代理人の同意を得るか又は法定代理人が未成年者に代わってこれらの行為をする必要があります。
Q43:相続の放棄は、他の相続人に対する意思表示をもってしなければならない?
A43:誤り。
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。民法上で定められている相続放棄の方式はこれだけです。
つまり、一般的には共同相続人全員による遺産分割協議の席で、相続分を放棄する(当該相続人自身は相続分を持たない旨の意思表示をする)という使い方をすることもありますが、これは民法上の相続放棄には該当しないということになります。
Q44:特定の相続人の利益のためにのみ相続の放棄をすることができる?
A44:誤り。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなします(民法939条)。
つまり、相続の放棄という行為は、放棄の申述をした者自身が相続人とならなかったとみなされるだけであり、特定の相続人に自己の相続分を寄与させるようなことはできません。
Q45:甲が死亡し、その子である乙及び丙のために相続が開始した。この事例で、甲が相続人らによる相続の放棄を禁止したときは、相続人らは相続の放棄をすることができない?
A45:誤り。
相続の承認・放棄は、相続人の自由意思によって判断されるべきものです。たとえ被相続人が自己の財産の相続放棄を禁止する遺言を残したとしても、法律的な拘束を生じません。
また遺言によってすることができる事項は、例えば下記のように法定されていますが、相続の承認・放棄の指示は、遺言によってすることができる事項には含まれていません。
遺言によってすることができる事項の一例
・未成年後見人および未成年後見監督人の指定(民法839条、民法848条)
・遺産分割の方法の指定とその委託(民法908条)
・遺産分割の禁止(民法908条)
・遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定(民法914条)
Q46:甲が死亡し、その子であるA、B及びCのために相続が開始した。この事例で、Aが相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合、Aの相続人Xは、A−X間の相続を放棄し、甲−A間の相続を承認することができる?
A46:誤り。
甲の相続人Aが、3箇月の熟慮期間内に当該相続の承認・放棄の意思表示をしないで死亡した場合には、Aの相続人であるXは、自己の熟慮期間内に、Aの相続について承認・放棄の意思表示をする必要があります。
さて、この事例において、Xが放棄の意思表示をするパターンとしては、以下の2種類が考えられます。
(1)Aの相続を全部放棄する。つまり、甲−A間の相続についても全て放棄する。
(2)甲−A間の相続については放棄するが、それ以外のAの相続については相続を承認する。
この事例を見てみますと、A−X間の相続を放棄していますので、(1)に該当することになりますが、そうしますと、甲−A間の相続の承認自体が全く意味のない事となりますので、結果として承認することはできないということになります。
Q47:錯誤により家庭裁判所に相続の放棄の申述をした相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月を経過したときは、その無効を主張することはできない?
A47:誤り。
要素の錯誤とは、契約などの法律行為の重要な部分に思い違いがあり、それがなかったら当該法律行為をしないのが普通であろうと考えられるような錯誤のことを言います(民法95条)。
錯誤がありますと、家庭裁判所への相続放棄の申述自体が無効として扱われることになります。そして、錯誤による無効を主張する期間には制限がありませんので、熟慮期間の3箇月を経過した後でも、無効の主張は可能となります(民法95条)。
Q48:相続放棄の申述を詐害行為として、相続人の債権者は取り消すことはできない?
A48:正しい。
相続の承認・放棄という法律行為は、身分行為である一身専属権の一種です。たとえ財産的な側面があるにせよ、第三者である債権者には何らの権利を行使することはできません。
よって、相続の放棄をすることで、たとえ当該債権者が不利益を負うことになるとしても、相続放棄の申述を詐害行為、つまり債権者を害する行為として取消しを主張することはできません。
Q49:兄弟姉妹である相続人は、遺留分として被相続人の財産の2分の1を受ける?
A49:誤り。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に対して保障された、受け取ることのできる最小限度の割合をいいます。よって、この部分に関しては、被相続人の遺言によっても、侵害できないことになります。
この遺留分が定められている理由としては、被相続人の財産を期待している相続人の生活を保障するためです。
民法では、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける(民法1028条)と規定しています。
(1)直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
(2)前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
よって、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分を有しないことになります。
Q50:包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するが、遺留分は有しない?
A50:正しい。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受けます(民法1028条)。
(1)直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
(2)前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
包括受遺者とは、遺言によって定められた一定の割合で、遺産を取得する者をいい、原則として相続人と同一の権利義務を有します(民法990条)。
しかし、包括受遺者は相続人ではありませんし、一定の相続人に対し被相続人の財産の一定割合を確保することによる生活保障という遺留分の趣旨の観点からも、包括受遺者には遺留分を認めていません。
Q51:遺留分額算定の基礎となる財産の額には、共同相続人中に被相続人から結婚、養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その贈与の時期にかかわりなくその価額がすべて算入される?
A51:正しい。
遺留分算定の基礎となる財産については、被相続人が相続関始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する(民法1029条1項)と規定しています。
この条文の「贈与した財産の価額」の中には、以下のものが含まれます。
(1)相続開始前の1年前にした贈与の全て(民法1030条)
(2)負担付贈与(目的の価額の中から負担の価額を控除したもの)(民法1038条)
(3)相続人が被相続人から結婚、養子縁組のため、若しくは生計の資本として受けた贈与(民法1044条、民法903条)
(4)不相当な対価をもってした有償行為(ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていたものに限る)(民法1039条)
今回の事例では、上記(3)に該当しますので、遺留分額算定の基礎となる財産の額に含まれることになります。
A52:誤り。
簡単に図示すると以下の通りです。
(死)A=B
|
(廃除)C=D
|
E
Cは兄弟姉妹以外の相続人に該当しますので、本来は遺留分権利者なのですが、廃除(民法892条)をされていますので、相続人とはなりません。
この場合、Cの子であるEが、Cの代襲相続人となりますので、遺留分の権利についても代襲相続することになります(民法887条2項)。
さて、遺留分権利者の権利として、遺留分減殺請求権があります。
遺留分減殺請求権とは、遺留分の権利者である相続人の相続分が、自己の遺留分を下回る場合に、生前贈与や遺贈を受けた人から、遺留分を取り戻す請求をすることができる権利です。
民法では、遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条の贈与(相続開始前の1年間にした贈与・悪意のある贈与)の減殺を請求することができる(民法1031条)と規定してます。
この事例におけるEは、Cの代襲相続人として、被相続人Aの相続財産について、遺留分減殺請求権を行使することができることになります。
Q53:遺留分権利者による減殺請求は家庭裁判所の許可を要する?
A53:誤り。
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び相続開始前の1年間の贈与、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与の減殺を請求することができます(民法1031条)。
遺留分減殺請求権の行使方法ですが、判例では、この権利は形成権であり、その行使は受遺者又は受遺者に対する意思表示によってなせば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はないとしています(最判S41.7.14)。
よって、減殺請求時に裁判所の許可を得る必要はないということになります。
Q54:遺贈は、贈与を減殺した後でなければ、減殺することができない?
A54:誤り。
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができません(民法1033条)。
これは、贈与が被相続人の生前に行われていることから、贈与を先に減殺してしまいますと、例えば受け取ったものをすでに費消してしまっている等、受贈者に対する負担が大きくなってしまう場合があります。
一方、遺贈は、被相続人の死亡後に効力を生じるものですので、減殺しても、受遺者の負担は受贈者の負担よりは影響が少ないと考えられるためです。
Q55:複数の遺贈がある場合には、遺留分権利者はその1つを選択して遺留分全部を減殺することができる?
A55:誤り。
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺します(民法1034条本文)。
これは、遺留分権利者に自由に選択権を与えますと、受遺者間に不平等が生じる可能性があるためです。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います(民法1034条但書)。
Q56:遺留分減殺請求が行使された場合、受贈者は、その返還すべき財産のほか、なお、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない?
A56:正しい。
遺留分減殺請求が行使された場合、受贈者は、その返還すべき財産のほか、なお、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければなりません(民法1036条)。「減殺請求があった日以後」というところに注意が必要です。
Q57:遺留分減殺を受けるべき受遺者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する?
A57:正しい。
減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰します(民法1037条)。
つまり、減殺を受けるべき受遺者が無資力であれば、その者から遺留分を取り戻すことは不可能です。
では、その分を別の受遺者(更に前の受遺者)に対して減殺請求することで取り戻すことができるのかといいますと、これはできません。
といいますのは、この別の受遺者にとってみれば、他の受遺者の無資力といった予測しない事柄によって不測の損害を受ける恐れがあり、この者を保護しなければならないからです。
よって、結局は遺留分権利者が無資力による損失分の負担をすることになります。
Q58:被相続人が自己所有の財産を不相当な対価で売却した場合、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときであっても、遺留分権利者は、これを減殺することができない?
A58:誤り。
不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなします(民法1039条前段)。
ちなみに、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければなりません(民法1039条後段)。
Q59:遺留分減殺請求権の1年の短期消滅時効の起算時は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時である?
A59:正しい。
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法1042条前段)。
いつまでも遺留分減殺請求権を行使できるとしますと、受贈者や受遺者の権利を喪失させる可能性が継続することとなり、取引の安全性を害することになるためです。
尚、この短期時効については、判例で、単に贈与や遺贈があったことを知っただけではなく、遺留分を侵害し、減殺できるものであることまで認識したときからであるとしています。
また、相続開始の時から10年を経過したときも、時効消滅します(民法1042条後段)。
Q60:遺留分を放棄しても、相続人であることには変わりはない?
A60:正しい。
遺留分を放棄しても、相続人であることには変わりはありません。よって、包括承継や相続の放棄も当然にすることができます。
Q61:相続開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の申述が必要である?
A61:誤り。
「申述」ではなくて「許可」です。相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じます(民法1043条1項)。
遺留分の放棄は、相続開始前において自由に出来るとしますと、債権者等から不当な圧力をかけられて遺留分の放棄を強制されられる等の問題が生じかねませんので、家庭裁判所の許可を必要としています。
ちなみに、相続開始後の遺留分の放棄は自由ですので、家庭裁判所の許可も不要となります。
尚、相続の放棄は、相続開始前にしても無効となります。
相続の放棄と遺留分の放棄の違いを以下にまとめてみましたので参考にしてください。
| 放棄 | 相続開始前 | 相続開始後 |
| ・相続 | ×(出来ない) | ○(家裁への申述が必要) |
| ・遺留分 | ○(家裁の許可が必要) | ○(許可も申述も不要) |
Q62:共同相続人の1人が遺留分を放棄すると、他の遺留分権利者の遺留分がそれだけ増加する?
A62:誤り。
共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません(民法1043条2項)。
これは、遺留分を定義している民法1028条からもわかることですが、遺留分は遺留分権利者個々人に対し、相続財産の一定割合を権利として定めたものですから、他の遺留分権利者の放棄に影響を受けることはありません。
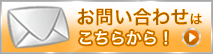 |
| NEXT→養子縁組Q&A集 |