後見・扶養Q&A
Q1:未成年後見人の場合にも、成年後見人の場合にも、後見人は必ずしも裁判所の選任により就任するとは限らない?
A1:誤り。
後見人には2種類あり、未成年者に対する後見人(未成年後見人)と、成年被後見人に対する後見人(成年後見人)に分けられます(民法838条1項)。
未成年者も成年被後見人も社会的弱者として、法的に保護の必要があるためです。
未成年者後見の場合について考えてみますと、例えば、両親ともに親権を剥奪された場合には、例外を除いて、家庭裁判所によって後見人が選任されます(民法841条)。
その例外として挙げられているのは、未成年者に対して最後に親権を行う者が、遺言で後見人を指定することができる(民法839条1項本文)というものです。
一方、成年後見人については、家庭裁判所が、後見開始の審判をする際に、成年後見人を選任する(民法843条1項)ことになっており、これには例外がありません。よって、成年後見人については誤りであるということになります。
Q2:未成年後見人の数は1人でなければならないが、成年後見人の場合は1人でなくてもよい?
A2:正しい。
未成年後見人は、1人でなければなりません(民法842条)。
これは、第三者が未成年者の身上監護と財産管理をする以上、複数で担当した場合に意思決定に時間がかかったり、考えや方向性にギャップがあった場合など、子に不利益をもたらす恐れがあることや、何か問題が起こったときに責任が不明確となる恐れがあるためです。
一方の成年後見人については、このような条文がなく、複数人であっても構いません。例えば、痴呆の高齢者の場合、監護については福祉関係の専門家が担当し、財産管理については法律家などが担当した方がより良いという場合もありえるためです。
Q3:家庭裁判所は、夫婦の一方に後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任する?
A3:正しい。
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任します(民法843条1項)。
夫婦の一方が成年被後見人となる場合には、夫婦の他方に後見人となってもらう場合が多いとは思いますが、それが不適当な場合もありますので、あくまでも家庭裁判所による選任という形をとることになります。
Q4:未成年後見人は、正当な事由がなくても辞任することができるが、成年後見人は、正当な事由がなければ辞任することができない?
A4:誤り。
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます(民法844条)。この条文は、未成年後見人と成年後見人の双方ともに適用されます。
後見人は、弱者である被後見人を法的に守っていく使命を帯びていますので、正当な事由なしに勝手に辞任されてしまいますと、被後見人が不利益を被ることになるからです。
Q5:未成年の父は、その非嫡出子の後見人となることはできない?
A5:正しい。
後見人の欠格事由として、以下の者は後見人になれないと規定されています(民法847条)。
(1)未成年者
(2)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
(3)破産者
(4)被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
(5)行方の知れない者
この事例の場合は、(1)の未成年者に該当しますので、後見人となることはできません。
未成年者が後見人になれない理由としては、当該未成年者自身が親権に服しており、法的保護を受けている状況ですので、その者が後見人になるというのは能力的に無理であるためです。
Q6:Aが婚姻関係にないBの子Cを認知した場合、AはCに対して扶養義務を負う?
A6:正しい。
扶養とは、例えば家族などの一定の近親者の生活を援助し、或いは養うということをいいます。
ちなみに、民法で定めているのは、私的扶養と呼ばれるもので、国が最小限度の生活を保障する生活保護(公的扶助)とは別のものです。
そして民法877条1項では、扶養義務者として、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があると定めています。
この事例では、AがCを認知をすることにより、A-C間で法律上の親子関係が生じることになり、直系血族として互いに扶養の義務が生じることになります。
Q7:AはCの弟であり、BはCの子であるが、Bの親族としては他に母Dがいる場合、AはBに対して扶養義務を負うことがある?
A7:正しい。
直系血族間および兄弟姉妹については、互いに扶養義務を負います(民法877条1項)。
この事例におけるA-Bの関係は、3親等の傍系血族に当たりますので、この条文からすれば該当しないことになります。
しかし、例外として、特別の事情がある場合には、家庭裁判所の審判によって、3親等内の親族間においても扶養義務を負わせることができる(民法877条2項)と規定されています。
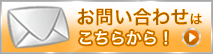 |
| NEXT→民法(総則)Q&A集 |