遺言・相続

遺言
遺言は、民法によると「普通方式の遺言」と病気や船舶遭難などにより死亡の危急に迫っている場合にする「特別方式の遺言」があります。
「普通方式の遺言」の種類には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つがあります(民法967条)。
★自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言をすべて自書してする遺言であり、公証役場での手続(公正証書参照)や証人の立会いを必要としない遺言です。
自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に作成できますが、以下の通りに民法が定める方式を守らなければなりません。
●自筆証書遺言の方式
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。
遺言は本文だけでなく、添付書類も自書する必要があります。判例では、自筆証書遺言に添付された不動産目録が、タイプ印書された事案において、自筆証書遺言の効力を生じないとした裁判例があります。
そして、遺言書に記入ミスがあったときは、訂正箇所を修正液などで訂正するのではなく、訂正箇所に下記の通りの手続を行って訂正する必要があります。
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません(民法968条2項)。
●自筆証書遺言をする際の注意点
◇日付
遺言書の日付は正確に記載する必要があります。
| 日付が正確な例 | 日付が不正確な例 | |
| ○平成17年1月1日 | ×平成17年1月某日 | ※どちらも、「日」が特定されていません |
| ○2005年1月1日 | ×2005年1月吉日 | |
◇添え手
遺言者を補助するために添え手をした者によってなされた遺言は、添え手をした者の意思が遺言に入りやすいと考えられます。又、添え手を無効とした判例もあります(最判昭62.10.8)。
◇自筆証書遺言での紛争防止
自筆証書遺言の作成は、公証役場での手続(公正証書参照)を経ないため、万一、遺言に不備があっても、遺言者は気づかないまま作成を終えてしまうことも考えられます。
例えば、遺言の加除訂正については、民法は上述のように、通常の訂正方法とは異なる厳格な方式を定めていて、それに従う必要があります。複数の遺言が存在したときに、日付があいまいだと、どの遺言が優先されるのかが争いになることも考えられます。
また、添え手をしてもらって自筆証書遺言すると、遺言の内容に添え手をした者の意思が介入したのではないかと、こちらも遺言がもとで争いになることが考えられます。
したがって、遺言をする場合には、自筆証書遺言よりも公正証書遺言をするほうが安全です。
★秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が自分で書くかまたは他人に書いてもらった証書に署名、押印して、その証書を封印し、そのうえで遺言者が公証人及び2人以上の証人の前に封書を提出して、自己の遺言者である旨ならびにその筆者の氏名及び住所を申し述べる方式の遺言のことです。
※公証人とは→公正証書のページ参照
秘密証書遺言は、全文を自筆で作成することが要求されていませんので、パソコンやワープロを利用して作成することができます。ただし、証書に署名・押印するのは遺言者自身が行わなければなりません。
秘密証書遺言の特徴として、公証役場での手続を必要としますが、封印してあるため、公証人や証人に遺言の内容を知られることがないという点があげられます。
●秘密証書遺言作成の手順(民法970条)
(1)遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと(民法970条1項1号)。
(2)遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること(民法970条1項2号)。
(3)遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること(民法970条1項3号)。
遺言者以外の者が筆者である場合は、その者の氏名・住所を申述しなければなりません。ちなみに、遺言の内容を筆記した筆者がワープロを操作して遺言書の表題と本文を入力し印字した場合において、遺言者が、公証人に対して、遺言書の筆者の氏名と住所を申述しなかったため、遺言を無効とした判例があります。
●加除訂正の方法
加除訂正の方法は、自筆証書遺言と同様です。秘密証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません(民法970条2項)。
●秘密証書遺言を作成する際の「証人」について、民法では次の者は証人になれないと規定しています(民法974条)。
◇未成年者(民法974条1項1号)
◇推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族(民法974条1項2号)
◇公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人(民法974条1項3号)
※受遺者(じゅいしゃ)とは、遺言で遺産を与えられる者のこと。
●言語が不自由な者がする秘密証書遺言
言語が不自由な者がする秘密証書遺言について、民法は次のように規定しています(民法972条)。
◇「口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書」することとしています。
◇言語が不自由な者が遺言をするには、法改正以前は公証人と証人の前で「封紙に自書」することとなっていましたが、現在は、「封紙に自書」することも「通訳人の通訳」により遺言をすることもできるようになっています。
●遺言の開封について
◇普通方式の遺言(自筆証書遺言、秘密証書遺言および公正証書遺言)のうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所に提出して、検認という手続を経て開封することができます(民法1004条)。
※検認とは、遺言書が偽造・変造されることを防ぐため家庭裁判所に提出して遺言書を保存する手続のこと。
※家庭裁判所一覧表参照
◇この場合、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に提出する必要があります。
遺言書の保管者がいない場合において、相続人が遺言書を発見したときも、遅滞なく、家庭裁判所に提出する必要があります。
◇「遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する」(民法1005条)とありますので、注意が必要です。ただし、上記に違反しても、遺言の効力に影響はないとされています。
公正証書遺言とは、遺言者が証人の立会いのもと、遺言内容を公証人に口述して、公証人がそれを筆記して作成する遺言です。
●作成の手順
民法969条では、「公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない」と規定されています。
(1)証人2人以上の立会いがあること。
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(くじゅ、注1)すること。
(3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
(5)公証人が、その証書は前各号(1〜4)に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
ちなみに、公正証書遺言を作成するには、上記の5つの方式とは別に、戸籍謄本や印鑑証明書などの書類を用意しておく必要があります。
注1:口授(くじゅ)=口述すること。
●公正証書遺言作成のメリット
公正証書遺言を作成すると、その原本は公証役場に、正本は遺言者が保管することになります。
したがって、万一、遺言者が正本を失くしてしまったときでも、原本が公証役場に保管されていますので安心です。この点が公正証書遺言を作成するメリットの一つでもあります。
| 原本、正本、謄本の違い | |
| 原本(げんぽん) | 正本や謄本のもとになる文書のこと。公正証書遺言の場合には、原本が公証役場に保管される。 |
| 正本(せいほん) | 原本に基づいて作成された文書のこと。公正証書遺言の場合には、遺言者が正本を保管する。 |
| 謄本(とうほん) | 原本を複写した文書のこと。 |
●公正証書遺言を作成する費用
公正証書遺言を作成するには、「公証人手数料令」の規定により、「証書作成手数料」と「遺言手数料」がかかります。
・証書作成手数料についてはこちらを参照→公正証書
・遺言手数料は、11,000円ですが遺産の総額が1億円を超える場合にはかかりません(公証人手数料令19条)。
★遺言は、普通方式の遺言3つ(自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言)以外として、特別方式の遺言があります。
民法が定める特別方式の遺言には、死亡危急者遺言(民法976条)、伝染病隔離者遺言(民法977条)、在船者遺言(民法978条)、船舶遭難者遺言(民法979条)の4つがあります。
相続
土地家屋等の資産価値はバブル期と比べてかなり下落したものの、高齢社会を背景とした死亡者数の増加を反映して、相続紛争は増加傾向が続いています。特に遺産分割をめぐる紛争の増加が著しく、遺産をめぐっての骨肉の争いが家庭裁判所に持ち込まれています。まさしく「相続」ならぬ「争族」の様相を呈しています。
★相続とは?
相続とは、人が死亡した場合に、その死者と一定の親族関係に立つものが、その財産上の法律関係を法律上当然に承継することをいいます。なお、失踪宣告を受けた者は死亡したものとみなされる(民法31条)のでその宣告によって相続が開始します。
| 第1順位 | 配偶者、子 ※養子であろうと実子であろうと問いません。胎児も含まれますが、死体で生まれたときは相続できません(民法886条)。 |
| 第2順位 | 配偶者、直系尊属 |
| 第3順位 | 配偶者、兄弟姉妹 |
※配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
※まずは第1順位、それがいなければ第2順位、それもいなければ第3順位となります。
★法定相続分について(民法900条)
遺言による指定がない場合には、原則として法定相続分の割合で相続します。
| 第1順位(配偶者と子)の相続分 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
| 第2順位(配偶者と直系尊属) | 配偶者3分の2、直系尊属3分の1 |
| 第3順位(配偶者と兄弟姉妹) | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
※昭和56年1月1日以前の相続については旧法の相続分が適用されます(登記手続きの際に問題となることがあります)。
★法定相続と違う割合で相続したいときは、遺産分割という方法があります。
共同相続人は、分割禁止の定めがないかぎり、いつでも全員で分割の協議をすることができます(民法907条)。分割協議は、相続人全員でなされ、一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効になります。また、相続債務は遺産分割の対象になりません。ご注意ください。
★被相続人が遺言によって相続分を指定している場合でも遺産分割できるの?
原則はできます。明文にはありませんが、被相続人が遺言によって相続分を指定している場合であっても相続の放棄が認められていることから、共同相続人の協議によって指定と異なる分割をすることができると解されています。ただし、遺言執行者がいる場合はできません。遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分、その他遺言の執行を妨げる行為をすることができないとされているからです。
★相続の放棄について
相続について、必ず相続しなければならないとなると、中には借金ばかり相続してしまう人も出てくるかもしれません。これではあまりにも酷です。そこで、相続の放棄という制度があります。相続の放棄については、プラスの財産も相続することはできませんが、多額の借金を背負ってしまう人には有益な方法でしょう。
相続の放棄の効果として、相続の放棄をしたものは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。つまり、相続放棄をした者は相続開始当初から、相続財産を承継しなかったことになり、しかも、その効果は絶対的であって何人にもその効力を生ずることになります。
相続の放棄をしようとするものは考慮期間内(民法915条、民法916条、民法917条)にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。考慮期間内とは、自己のために相続が開始されたことを知ったときから3か月です。
よく勘違いされる方がいますが、相続の放棄は、他の相続人に対する意思表示をもってするものではありません。このような意思表示は全くの無効であり、効果を主張できませんので注意が必要です。あくまで、家庭裁判所に申述しなければならないのです。
相続の承認や放棄における相続の起算についての最高裁判例をご紹介しておきます。
「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」
つまり、相続の承認や放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行うだけでなく、被相続人の死亡の時以降、何年経過していても「自己のために相続の開始があったことを知った時(=相続財産の存在を認識した時)」から3か月以内に行う場合もあり得ることを意味しています。
※他にも下記に遺言・相続に関するトラブルの一例を挙げてみました。
| ◆ 遺言・相続に関する内容証明の例 |
|---|
| 遺産分割の話し合いを求める内容証明 |
| 遺産目録の提示を求める通知をする内容証明 |
| 遺産分割取消しの通知をする内容証明 |
| 遺言無効による遺産返還請求を通知する内容証明 |
| 相続遺留分の減殺を求める内容証明 |
| 遺言執行者に対する利害関係人の催告をする内容証明 |
| 遺言執行事務の処理状況を照会する内容証明 |
| 定期預金の遺贈を通知する内容証明 |
| 遺言執行者の任務終了を通知する内容証明 |
| 生命保険金受取人指定を通知する内容証明 |
| 相続人に対する不動産遺贈履行を請求する内容証明 |
| 相続回復請求の通知をする内容証明 |
| 相続廃除の警告をする内容証明 |
| 限定承認による債権申出を催告する内容証明 |
| 相続分取戻しの通知をする内容証明 |
※上記は一例であり、実際には様々な事実・利害関係があります。十人十色と言いますが、「私の場合はこうなのだけれど・・・」という場合は、渡辺行政書士事務所にご相談ください。内容証明に限らず、様々な提案をさせていただきます。
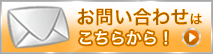 |
| NEXT→事故損害に関する内容証明 |