民法(総則)Q&A集
Q1:胎児(のちに死体で生まれた場合を除く)は、遺贈を受けることができる?
A1:正しい。
権利能力とは、権利義務の帰属主体となりうる地位・資格のことを指します。
この権利能力は、 自然人と法人に認められますが、自然人については、出生によって権利能力が始まる(民法3条1項)と規定されています。
よって、生まれる前の胎児には権利能力がないのですが、民法では、不都合が生じる場合の以下の3つについては、既に生まれたものとみなして、例外的に権利能力を認めています。
(1)損害賠償請求権
(2)相続
(3)遺贈
さて、この事例における遺贈については、胎児は既に生まれたものとみなされますので、胎児は遺贈を受けることができます(民法965条、民法886条1項)。
Q2:外国人は、法令又は条約に禁止又は制限が規定されている場合を除き、我が国においても権利能力を有する?
A2:正しい。
民法は、原則として日本国籍を持つ者を対象とした法律ですが、日本国籍を持たない外国人に対しても、原則として適用しています。
条文でも、外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する(民法3条2項)と規定しています。
よって、外国人も、法令又は条約に禁止又は制限が規定されている場合を除いて、原則として権利能力を有することとなります。
Q3:就学前の幼児が、他の者から贈与の申込みを受けてこれを受諾しても、その承諾は無効である?
A3:正しい。
意思能力とは、自分のする行為の結果について認識し、判断できる程度の精神的な能力のことをいいます。この意思能力が備わっていて、初めて法律行為が有効なものとされます。
法律行為とは、例えば物の売買などのように、その行為をすることによって、法律上の権利や義務が発生する行為のことをいいます。つまり、売買が成立しますと、売主は物の引渡し義務が発生し、代金を受け取る権利が生じます。一方、買主は、代金の支払い義務が発生しますが、その物を受け取る権利が生じます。
民法では、意思能力を有しない者(自らの意思を有しない者)は、法律行為をすることができず、その者のした法律行為は無効として取り扱います。一般には、意思能力が備わるのは、7〜8歳位といわれています。
一方、行為能力とは、単独で権利義務に関する行為を完全にすることができる能力をいいます。この行為能力を有しない者を、民法では制限能力者として取り扱い、これらの者を保護するようにしています。
制限能力者は、以下の4つになります。
(1)未成年者
(2)成年被後見人
(3)被保佐人
(4)被補助人(但し、民法17条1項の審判、つまり、特定の法律行為につき補助人の同意を得ることを要する旨の審判を受けた者に限る。)
さて、この事例における就学前の幼児は、行為能力どころか、意思能力をも有していないと考えられますので、この者を保護する必要から、この行為は無効となります。
Q4:未成年者がする取引についての法定代理人の同意は、未成年者自身に対してではなく、未成年者と取引をする相手方に対してなされても有効である?
A4:正しい。
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければなりません(民法5条1項)。
未成年者は制限能力者に該当しますので、未成年者が法律行為をする場合には、原則として法定代理人(一般的には両親)の同意が必要です。
では、この法定代理人の同意は、誰に対してする必要があるのかといいますと、通説として、未成年者自身に対してしてもいいですし、法律行為の相手方に対してしても構わないとされています。
Q5:未成年者が、債務を免除される旨の債権者からの申込みを承諾するには、法定代理人の同意を得ることを要しない?
A5:正しい。
未成年者が法律行為をする場合には、原則として法定代理人の同意が必要となります(民法5条1項本文)が、その例外として、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない(民法5条1項但書)と規定しています。
この事例における「債務の免除の承諾」という法律行為は、その結果、単に支払義務を免れるだけですので、民法5条1項但書が適用され、法定代理人の同意は不要となります。
Q6:未成年者が負担付きの遺贈の放棄をするには、法定代理人の同意を要しない?
A6:誤り。
遺贈とは、遺言者が遺言でその財産の全部または一部を無償で譲与するものです。
負担付き遺贈とは、受遺者(遺贈によって遺産を受け取る者)に一定の義務(負担)を課した遺贈のことをいいますが、負担付きとはいえ、遺贈の放棄をしますと、遺贈を受ける利益を失うことになりますので、「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」(民法5条1項)とはいえません。
よって、遺贈の放棄をするためには、法定代理人の同意が必要となります。
Q7:未成年者の法定代理人がその未成年者の営業を許可するについては、営業の種類まで特定する必要はない?
A7:誤り。
未成年者が法律行為をする場合には、原則として法定代理人の同意が必要となります(民法5条1項本文)。
この事例における「営業」というものについても、例えば資金を借り入れたり、商品を仕入れたり販売したりという様々な法律行為が絡んでいますので、原則として法定代理人の同意が必要となります。
しかし、その都度、この営業に関する同意を得るというのでは、実際には煩雑すぎて困難です。
よって、事前に法定代理人による営業の許可があれば、その許可の範囲内においては成年者と同じ行為能力があるとし、法定代理人の同意が不要となります。つまり、その範囲における法定代理人の代理権が消滅することになります。
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有します(民法6条1項)。
この条文における「一種または数種」というのは、社会通念上の営業の種類の1個または数個という意味ですので、この「営業の種類」を特定した上で、営業を許可しなければならず、例えば、どんな種類の商売でもやっていい、というような許可は認められないことになります。
また、1個の営業の一部のみを許可することも認められません。
Q8:未成年者の被保佐人が婚姻をしても、被保佐人としての行為能力の制限は解除されない?
A8:正しい。
被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者(民法11条)を言います。簡単に言いますと、法律行為をするための判断能力が不十分な者に該当し、制限能力者として保護されている者です。
さて、未成年者が婚姻したときは、これによって成年に達したものとみなされます(民法753条)。
よって、未成年者としての行為能力の制限は婚姻によって解除されることになりますが、被保佐人としての行為能力の制限は、婚姻とは無関係ですので、そのまま残ることとなります。
Q9:成年被後見人の行為(日用品の購入その他日常生活に関するものを除く)は、成年後見人の同意を得てしたときは、取消すことができない?
A9:誤り。
成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、後見開始の審判を受けた者をいいます(民法7条、民法8条)。
例えば、精神障害者や、高齢者でいわゆるボケが進んでしまったため、自分の行為の結果について正確に認識できず、判断ができない状況がずっと続いているような人をイメージしていただくとわかりやすいかと思います。
このような人が単独で法律行為をしても、正確な判断ができませんので、不利益を被ることがありえます。そこで、民法では、制限能力者のカテゴリーに入れ、成年後見人という保護者をつけることで、この者たちを保護しています。
そして、成年被後見人は、例え成年後見人の同意を事前に得たとしても、その同意の内容どおりに行動できるかどうかがわからないため、未成年者以上に保護の度合いを強くしており、結果、成年後見人の同意をもってしても、単独で法律行為をした場合には、その行為は後日取消すことができるとしています。
ちなみに、この取消は絶対的なものであり、善意の第三者にも対抗できます。
尚、日用品の購入その他日常生活に関するものの購入(売買行為)までを制限するのは酷であるため、それらについては単独で有効な法律行為をすることができるとしています。
Q10:後見開始の審判及び補助開始の審判は、いずれも、本人が請求をすることができる?
A10:正しい。
被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者で、補助開始の審判を受けた者をいいます(民法15条1項、民法16条)。
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者を、制限能力者(成年被後見人、被保佐人、被補助人)として保護するためには、家庭裁判所における各々の審判の手続きが必要となります。
そして民法では、以下の通りに後見開始の審判及び補助開始の審判の各請求権者を定めています。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができます(民法7条:成年被後見人)。
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができます(民法15条1項本文:被補助人)。
よって、双方の審判とも、「本人」が請求することができます。
A11:正しい。
被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者で、家庭裁判所が保佐開始の審判をした者をいいます(民法11条本文)。
被保佐人は、成年被後見人よりは程度が軽いとはいえ、事理の弁識能力が著しく不十分な者ですから、成年被後見人の場合と同じく、制限能力者として取り扱い、保護する必要があります。
よって、被保佐人には保佐人を付する(民法12条)こととしています。
ちなみに、被保佐人よりも更に程度の軽い被補助人の場合にも、補助人という法定代理人が必ず付く事になります(民法16条)。
A12:誤り。
被保佐人が法律行為をする場合は、原則として単独で有効にすることができますが、制限能力者として保護をする必要がありますので、一定の場合には、保佐人の同意が必要とされています。
被保佐人が次に掲げる行為をするには、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、その保佐人の同意を得なければなりません(民法13条1項)。
(1)元本を領収し、又は利用すること(民法13条1項1号)。
(2)借財又は保証をすること(民法13条1項2号)。
(3)不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること(民法13条1項3号)。
(4)訴訟行為をすること(民法13条1項4号)。
(5)贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること(民法13条1項5号)。
(6)相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること(民法13条1項6号)。
(7)贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること(民法13条1項7号)。
(8)新築、改築、増築又は大修繕をすること(民法13条1項8号)。
(9)第602条に定める期間を超える賃貸借をすること(民法13条1項9号)。
この事例における「自動車の売却」は、民法13条1項3号の「重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」に該当しますので、保佐人の同意又はこの同意に代わる家庭裁判所の許可が必要となります。
よって、被保佐人が単独でした当該自動車の売買契約は取消すことができます。
なお、民法では、取引の安全性を担保するために、善意の第三者(法律行為に何らかの瑕疵があり、取消しができる場合に、当該取消し前に利害関係を持った者で、当該取消理由を知らない者)については、優先して保護をしようという立場なのですが、制限能力者の保護を優先するという観点から、この事例のような場合には、売買契約の取消しが優先されることになります。
よって、善意の第三者に転売された後でも、取消しをすることができます。
Q13:家庭裁判所は、保佐開始の審判において、保佐人の同意を得ることを要する法定の行為に関し、その一部について保佐人の同意を得ることを要しない旨を定めることができる?
A13:誤り。
被保佐人が保佐人の同意を得ることを要する法律行為は、民法13条1項に列挙されています。
これらの法律行為について保佐人の同意を不要とすることは、民法上認められていませんので、家庭裁判所においても、そのような例外を定めることはできません。
Q14:保佐人の同意を得ることを要する行為につき、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのに同意をしない場合には、被保佐人は、家庭裁判所に対し、保佐人の同意に代わる許可を求めることができる?
A14:正しい。
被保佐人の同意を必要とする行為(民法13条1項各号)や、保佐開始の審判において、同意を必要とする行為を増やした場合の当該行為(民法13条2項)については、保佐人の同意が必要となりますが、これらの行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができます(民法13条3項)。
Q15:成年被後見人は、成年後見人が追認した行為も取消すことができるが、被保佐人は、保佐人が追認した行為を取消すことができない?
A15:誤り。
追認とは、とりあえずは有効となっている取り消し可能な法律行為について、取消権を有する者(取消権者)が改めて有効であることを認めることにより、取消権を放棄することをいいます(民法122条)。
行為能力の制限によって取消すことができる行為について追認ができる者(追認権者)は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者とされています(民法120条1項)。
よって、成年後見人や保佐人、補助人という法定代理人は、追認をすることができることになります。
さて、追認権者が追認をしますと、制限能力者のした法律行為は初めから有効なものとみなされますので、その後は取消しをすることはできなくなります(民法122条)。
よって、成年後見人が追認した行為については、成年被後見人がその後取消しをすることはできません。
Q16:保佐人及び補助人は、いずれも、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為についての代理権を付与されることがある?
A16:正しい。
保佐人については、家庭裁判所は、第11条本文に規定する者(保佐開始の審判の請求権者)又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます(民法876条の4第1項)。
つまり、保佐人には、元々被保佐人の代理権は付与されておらず、同意権しか付与されていないのが原則です。
この例外として、家庭裁判所の審判により、保佐人に対し、特定の法律行為についての代理権を付与することができるとしています。ちなみに成年後見人には、代理権が付与されています。
補助人についても、家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者(補助開始の審判の請求権者)又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる(民法876条の9第1項)としています。
つまり補助人についても、保佐人と同様に代理権は元々与えられていませんので、家庭裁判所の審判により、代理権を付与してもらうことができるということになります。
Q17:Aが未成年者Bに建物を売却し、その後にBが成年に達した場合において、AがBに対して追認をするかどうか確答するよう催告し、Bが所定の期間内に確答を発しないときは、追認をしたものとみなされる?
A17:正しい。
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項における、被補助人が特定の法律行為をする場合における補助人の同意を要する旨の審判を受けた被補助人をいう。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます(民法20条1項前段)。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなします(民法20条1項後段)。
この事例の場合、Bが未成年者の時にした建物売却という法律行為は、法定代理人の同意がない以上は、取消うべき行為となります。
しかし、取引の相手方であるAとしては、いつまでも取消可能な不安定な状況が続きますと、非常に困ってしまいます。また、制限能力者の保護が優先されることから、相手方は善意であっても保護されず、不利益を被る可能性が高いといえます。
よって、民法では、このような法的に不安定な状況を解消させるために催告という制度(民法20条各項参照)を定めています。
この事例では、Aが催告をしようとする時点では、すでにBは成年になっていますので、自分自身で有効に法律行為をすることができる能力者となっていますし、意思表示の受領能力もあります(民法98条の2の反対解釈)。
よって、Aは直接Bに対して催告をすることができ、Bも、1人で判断できますので、民法20条1項の定めのように、1箇月以上の期間を定めて催告をすれば、その期間内に確答を発信しないときでも、Bが当該行為を追認したものとみなして構いません。
A18:誤り。
丙は、催告を受けた時点において未成年者です。
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項(民法20条1項)に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなします(民法20条2項)。
一方、未成年者に対する催告は、未成年者に意思表示の受領能力がないことから、何らの確答がない場合でも、追認したものとみなすことはできません(民法98条の2参照)。
A19:正しい。
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなします(民法20条2項)。
法定代理人に対して催告した場合、当該法定代理人は意思表示の受領能力があり、また単独で追認をすることができますので、期間内に確答が得られない場合には、取消権を放棄したものと考えられ、追認したものとみなされます。
A20:誤り。
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、1箇月以上の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができます。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなします(民法20条4項)。
この事例においては、被保佐人が催告を受けていますが、この者は単独で有効に追認をすることができませんので、たとえ1箇月以上の期間を開けて催告をしたとしても、その者からの通知がないからというだけで、追認とみなすことはできません。
尚、この民法20条4項の条文では、「追認を得るべき旨」となっており、民法20条1項の「追認するかどうか」とは異なっておりますので注意が必要です。
Q21:成年被後見人又は被保佐人が、相手方に能力者である旨を誤信させるため詐術を用いた場合、成年後見人は、成年被後見人の行為を取消すことができるが、保佐人は、被保佐人の行為を取消すことができない?
A21:誤り。
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法21条)。
つまり、制限行為能力者が、自己が行為能力者であると相手方を誤信させるような欺罔的な行為をし、その結果、実際に相手方が誤信した場合までも、当該制限行為能力者を保護する必要はないため、相手方を保護することにした訳です。
よってこの事例では、詐術を用いた当該成年被後見人の行為について、成年後見人は取消すことができないということになります。
Q22:被保佐人は、第三者が銀行から融資を受けるにあたり、自己が被保佐人であることを告げないでその債務を保証したときは、当該保証契約を取消すことができない?
A22:誤り。
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法21条)。
この詐術は、積極的に用いた場合や、他の言動などと共に、相手方の誤信を強めさせたような場合は該当しますが、単に制限行為能力者であることを黙秘していただけでは、詐術には当たらないとする判例(最判S44.2.13)があります。
よってこの事例でも、単に被保佐人であることを告げないで黙っているだけですので詐術には当たらず、その後契約を取消すことができるということになります。
A23:正しい。
従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができます。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様です(民法25条1項)。
不在者の財産を管理する者(財産管理人)がいれば、不在者の財産を守ることができますので、本人や法律上の利害関係人にとっては不利益とはならず、問題にはなりません。
しかし、このような権限を持つ者が選任されていない場合には、一定の者が財産管理人の選任の請求をすることで、不在者の財産を管理させることができるということになります。
この場合の利害関係人とは、例えば債権者や相続人など、当該不在者の財産が不当に流出してしまうと影響が出る者(法律上の利害関係人)が該当し、単に近所に住む者や友人等は、請求することができません。
A24:誤り。
不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます(普通失踪:民法30条1項)。
よって、不在者が生死不明のまま7年間が経過すれば、利害関係人は、失踪宣告の請求をすることができます。この場合の利害関係人は、法定相続人や財産管理人等が該当し、配偶者も含まれます。
さて、不在者と離婚をするためには、必ずしも失踪宣告が必要かといいますと、そうではありません。
つまり、夫婦の一方は、離婚の訴えを提起することができますが、民法770条1項3号では、「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」と規定されています。
よって、不在者である配偶者との婚姻の解消には、必ずしも失踪宣告が必要ということにはなりません。
Q25:Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合において、Bが事故に遭遇してから1年が経過すれば、Aは家庭裁判所に対し、Bについての失踪宣告を請求することができる?
A25:正しい。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2種類があり、民法では以下の通り規定されています。
不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる(普通失踪:民法30条1項)。
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする(特別失踪:民法30条2項)。
この事例で問われているものは、特別失踪です。また、ここでいう利害関係人には、法定相続人や不在者財産管理人などが該当しますので、子Aは父Bの失踪宣告を請求することができます。
A26:誤り。
普通失踪の宣告を受けた者は、不在者の生存が最後に確認されたときから7年間が満了した時に、特別失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなします(民法31条)。
よって、この事例におけるBの死亡時点より前に配偶者Aが行ったBの財産の売却行為は、Bが生存している期間の法律行為ですので、無権代理行為(代理人の権利がないのに代理人と称して行った行為)に該当し、本人の同意がない以上は、有効となることはありません(民法113条1項)。
Q27:Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合において、Bが事故に遭遇する前に、既にBのために財産管理人が選任されている場合には、Aは、Bにつき失踪宣告の請求をすることができない?
A27:誤り。
財産管理人とは、従来の住所又は居所を去った者(不在者)が放置した財産(残留財産)を管理する人のことをいいます(民法25条1項参照)。
この財産管理人の制度は、不在者が生存していて、将来戻ってくることを前提とした制度であるため、その者の財産が不当に流出するのを防ぐだけで、当該不在者の死亡を擬制することはできません。
死亡の擬制ができませんと、身分関係の終了や相続が生じませんので、いつまでも法律上の安定が図れないということにもなりえます。よって、不在者の財産管理人がいたとしても、当該不在者の失踪宣告の請求はできることになります。
A28:誤り。
失踪者が生存すること又は失踪宣告により死亡したものとみなされた時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければなりません(民法32条1項本文)。
つまり、失踪宣告によって死亡したものとみなされた時期と異なる事実が判明した場合でも、当該失踪宣告を取り消しませんと、その事実だけでは変更されず、当該失踪宣告の効果がそのまま続いてしまうことになります。
よって、死亡時期の変更の場合でも、失踪宣告の取消を請求する必要があります。
ちなみに、失踪宣告が取り消された場合、原則は財産関係や身分関係が従前に戻ることになりますが、この例外として、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力には影響を及ぼさず(民法32条1項但書)、また、失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失うものの、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負います(民法32条2項)。
Q29:工場の賃貸の効力は、特約がない限り、その工場の所有者が備え付けたその所有者の機械に及ばない?
A29:誤り。
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とします(主物と従物:民法87条1項)。
そして、従物は、主物の処分に従います(民法87条2項)。
この「主物と従物」という概念は、2個以上の物がある場合において、その一方が他方の経済的効用を助ける場合には、できる限りその処分については同一の方向、つまり一緒に進めるのが望ましいというところから出てきています。
例えば、刀と鞘の関係では、刀が主物、鞘が従物であり、刀の所有権を移す場合には、従物としての鞘も一緒に移すのが望ましいということです。
この事例では、主物である工場を賃貸していますので、従物である当該工場内の機械にも、当該賃貸借の効力が及ぶことになります。
ちなみに従物の要件は、以下の通りです。
(1)主物とは別個独立のものであること。
(2)主物の常用に供せられること。
(3)特定の主物に付属すると認められる程度の場所的関係にあること。
(4)主物と同一所有者に属すること。
Q30:果樹の贈与の効力は、特約がない限り、その木に実った果実に及ばない?
A30:誤り。
果実のうち、物の用法に従い収取する産出物を天然果実とします(民法88条1項)。
そして、天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属します(民法89条1項)。
よって、贈与時点で樹木から分離していない果実については、果樹の一部ですので、果樹の贈与の効力は当該果実にまで及ぶことになります。
民法では「果実」について、天然果実と法定果実の2つを定義しています。
法定果実とは、物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を指します。例えば、土地の使用対価としての地代や、家屋の使用対価としての家賃、金銭の使用対価としての利子などが挙げられます。
そして、法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得することになります(民法89条2項)。
Q31:法律行為とは?
A31:法律行為とは、人が意思表示によって法律効果(物権的効果・債権的効果)を発生させる行為のことをいい、この法律行為の種類を大別すると以下の3つに分類できます。
(1)単独行為:単一の意思表示により構成される法律行為。相手方のない場合(遺言等)だけでなく、相手方のある場合(取消、解除等)もあります。
【具体例】
・寄付行為(民法41条)
・相殺(民法505条)
・債務免除(民法519条)
・遺言
(2)契約:2つ以上の相対立する意思表示の合致により成立するもの。双方行為ともいいます。
【具体例】
・売買
・死因贈与→死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のことをいいます(民法554条)。つまり、一般的な贈与と同じく、無償で与える側(贈与者)と受ける側(受贈者)との意思表示の合致が必要です。
(3)合同行為:数人が共同して同一目的に向かってする意思表示の結合によって成立するもの。
【具体例】
・社団法人の設立行為
Q32:甲が真意では買い受けるつもりがないのに、乙から土地を買い受ける契約をした場合において、乙が注意すれば甲の真意を知ることができた場合には、売買契約は無効である?
A32:正しい。
意思の欠缺(けんけつ)とは、法律行為である意思表示の行為はあるものの、その意思表示をした者の内心の意思(効果意思)が欠けているものをいいます。
この意思の欠缺の種類として、民法では以下の5つを規定しています。
(1)心裡留保(民法93条)
(2)通謀虚偽表示(民法94条)
(3)錯誤(民法95条)
(4)詐欺(民法96条)
(5)強迫(民法96条)
上記の5つに該当する場合、その意思表示が無効になったり取消可能となったりします。但し、心裡留保は原則有効です。
つまり、いったん有効に成立したかにみえる法律行為が、後日覆される可能性がありますので、取引の相手方からすれば、注意を要することになります。
今回の事例では、甲が自分自身で購入する意思がないのにも関わらず、乙に対して購入の意思表示をしています。簡単に言えば、甲が乙に嘘を言っているということになります。
もし、乙が甲の言葉を信じて行動を取った場合(例えば、売り渡しの準備を始めた場合等)、甲の嘘に対して不利益を被ることになります。
よって、民法では、この甲の行為を心裡留保として、嘘を付かれた乙を保護する、つまり甲の意思表示を有効とするとしています。
但し、嘘を付かれた乙が、その嘘を知っていた場合(悪意)や、気をつければ甲の真意を知ることが分かったとき(有過失)の場合は、乙を保護する必要はないとして甲の意思表示は無効としています。
この事例における乙は、善意ではあるものの過失がありますので、甲の意思表示は無効となります。
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする(心裡留保:民法93条)。
Q33:甲・乙間で甲の所有する土地を乙に売り渡す旨を仮装した後、乙が実情を知らない丙に転売した場合には、甲は乙から請求されれば、その土地を乙に引き渡さなければならない?
A33:誤り。
甲────→乙────→丙(善意)
仮装売買 転売
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とします(通謀虚偽表示:民法94条1項)。
この事例における甲乙間の売買は仮装ですので、甲から乙への売買は無効となります。乙も仮装であることを知っているわけですから、乙を保護してあげる必要はないということです。
よって、甲は、乙に対して当該土地の引渡しを拒むことができます。
A34:誤り。
A───────→B──────→C
仮装譲渡(土地) 賃貸(建物)
通謀虚偽表示とは、本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることをいいます。
そして、通謀虚偽表示の当事者は、お互いに仮装していることを知っている(=悪意)訳ですから、法律上で保護をする必要はなく、よって無効なものとして取り扱われます。当事者はお互い相手に対して無効を主張できます。
しかし、この仮装行為の後に利害関係を有する第三者が出てきた場合には、この者を法律的に保護してあげることが必要な場合も出てきます。
民法では、相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効となりますが、善意の第三者に対抗することができない(民法94条1項、民法94条2項)と規定しています。
この善意の「第三者」に該当する、つまり法律の保護を受ける者の具体例については、判例を見ていく必要があります。
◎第三者に該当する例
・不動産の仮装譲渡の譲受人から、その目的物を譲り受けた者
・不動産の仮装譲渡の譲受人からその目的物について抵当権の設定を受けた者
・仮装の抵当権者から転抵当権の設定を受けた者
・虚偽表示の目的物を差し押さえた仮装譲受人の債権者
・仮装の債権に基づいて仮装の質権を設定していた者の債権を質権とともに譲り受けた者
・所有者が不実の所有権移転登記がなされたことを知りながら放置している場合に、その登記名義人から当該不動産を譲り受けた者
◎第三者に該当しない例
・債権の仮装譲受人から取り立てのために債券を譲り受けた者
・土地賃借人が借地上の建物を仮装譲渡した場合の土地賃貸人
・土地の仮装譲受人からその土地上の建物を賃借した者
・代理人や法人の代表機関が虚偽表示をした場合の本人や法人
・1番抵当権が仮装で放棄された場合に、自己の抵当権が1番抵当権になったと誤信した2番抵当権者(通説)
この事例における第三者Cは、確かに善意ではありますが、日本の法律上は、土地と建物は別個の不動産として取り扱っており、Cは土地についての利害関係人ではありません。
よって、AがCに対して、当該土地の売却が無効であるとして、土地の明渡しを求めることができ、これに対してCは拒絶することはできません。
A35:正しい。
A────→B────→C────→D
仮装譲渡 譲渡 (悪意) 譲渡 (善意)
民法では、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効だが、善意の第三者に対抗することができない(民法94条1項、民法94条2項)と規定しています。
この条文における「第三者」は、この事例におけるCだけでなく、転得者であるDも含まれると判例(最判S45.7.24)は示してしています。
そして、一旦は悪意のCに譲渡されたとしても、その者から譲渡を受けたDが善意である以上は、この者は民法94条2項における第三者に該当する(相対的構成説)としています。
よって、善意のDを保護する必要がありますので、AはDに対して明渡し請求をすることはできないということになります。
A36:誤り。
(債権者)A─────→B(債務者)
│
│債権譲渡(仮装)
↓
C
判例では、虚偽表示に基づく仮装の債権譲渡における債務者は、仮装行為の後に新たに出現した第三者ではありませんので、民法94条2項の第三者には該当しないとしてます。
よって、債務者Bは、たとえ異議を留めない承諾(民法468条1項)をした後でも、AC間の債権譲渡が仮装であったことを主張して、譲受人Cへの支払い(弁済)を拒むことができます。
Q37:AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Aは、売買代金債権を善意のCに譲渡した。Bは、土地の売買契約が無効であるとして、Cからの代金支払請求を拒むことはできない?
A37:正しい。
仮装譲渡
A─────→B
│
│債権譲渡
↓
C
(善意)
判例では、虚偽表示に基づいて生じた仮装の債権を善意で譲り受けた者は、民法94条2項の第三者に該当するとしています。
よって、善意のCを保護するため、Bは、Cからの代金支払請求を拒むことができないということになります。
A38:誤り。
甲────→乙
(要素の錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とします(民法95条本文)。
錯誤とは、表意者の勘違いに該当するものですが、その全てを無効とするのではなく、あくまでも法律行為の要素に錯誤がある場合のみを無効としています。
つまり、要素の錯誤とは、意思表示の内容の重要部分についての錯誤であり、通常一般の人から見ても、そのような錯誤がなければそのような意思表示をしなかったと思えるような重大なものであるといえます。
さて、この事例における甲は、要素の錯誤によって売買契約を締結していますので、甲は乙に対して、要素の錯誤による無効を主張することができます。
本来、要素の錯誤による無効を主張できるのは、無効による保護を受ける表意者本人のみ(通説及び判例)なのですが、表意者に重過失がある場合まで当該無効を認めるのは保護し過ぎですので、この場合には無効の主張ができません(民法95条但書)。
判例では、表意者に重大な過失がある場合には、表意者本人だけでなく、相手方や第三者も原則として無効を主張することができない(最判S40.6.4)と示しています。
これは、表意者本人が無効を主張できない以上、他の人に当該無効の主張を認める必要性がないからです。よって、この事例における甲及び乙は、要素の錯誤による無効を主張することはできません。
Q39:甲と乙との間に売買契約が締結されたが、甲の意思表示は要素の錯誤に基づくものであった。この事例において、甲が錯誤による無効を主張する意思がない場合には、乙は、売買契約の無効を主張することができない?
A39:正しい。
錯誤による無効は、表意者を保護するために設けられた制度ですので、表意者本人が無効の主張をしないこと自体は自由です。
そして、その場合でも、相手方や第三者も原則として無効の主張ができない(最判S40.9.10)とされています。
しかし、例外的に、
(1)第三者において表意者に対する債権を保全するために必要がある。
(2)表意者自身が錯誤無効を認めている。
という2点を満たしている場合には、当該第三者は、表意者が錯誤による無効を主張する意思がなくても、錯誤無効を主張することができる(最判S45.3.26)としています。
A40:誤り。
甲─────→乙
(要素の錯誤)
善意・有過失
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とします。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができません(民法95条)。
甲は有過失ですから、要素の錯誤による無効を主張することができます。
無効により、始めから効力が発生しなかったこととなりますので、甲はその履行責任は免れることになりますが、過失がありますので、契約締結に関する過失責任を問われる可能性はあります。
よって、乙は、甲に対し、被った損害の賠償を請求する余地があるといえます。
Q41:相手方が資産家であると誤信し、それを動機として婚姻をした場合には、その動機が表示され、意思表示の内容となっていたときであっても、その婚姻について、錯誤による無効を主張することはできない?
A41:正しい。
意思表示をする動機に錯誤がある場合を「動機の錯誤」と言います。
判例では、この動機が相手方に明示又は黙示に表示されている場合に限り、法律上の要素の錯誤に該当する(最判S29.11.16)としています。
この事例では、動機の錯誤が成立しているように見えますので、要素の錯誤による無効が主張できるような気がしますが、身分行為については、民法95条の規定が適用されません。
すなわち、婚姻の無効原因(民法742条)は以下のものに限られています。
(1)人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
(2)当事者が婚姻の届出をしないとき。
つまり、身分行為の場合は、無効による影響が大きく、錯誤無効を認めてしまうと法律関係が不安定になるため、認めていないということになります。
A42:誤り。
C社従業員───→B───→A
(詐欺)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができます(民法96条1項)。
この「詐欺」が成立する要件としては次の通りです。
(1)相手方を欺罔して、錯誤に陥らせようとする故意があること。
(2)(1)の錯誤によって、意思を決定表示させようとする故意があること。
すなわち、2段階の故意が必要とされています。
そして、詐欺による取消しを主張するためには、上記の欺罔行為により実際に錯誤が生じ、その錯誤によって意思表示をしたこと及び当該詐欺行為が違法であることが必要となります。
さて、この事例におけるBですが、詐欺の要件である「故意」を欠いていますので、Bは詐欺には該当しません。よって、Aは詐欺による取消しを主張することはできません。
A43:誤り。
貸金債権
(債権者)A─────→B(債務者)
││
│└────→C(物上保証人)
│(抵当権設定)
↓ ※Bの詐欺による
D
(債権譲受人)
Bの詐欺による抵当権設定契約の当事者はAとCですので、この事例のような場合を、第三者による詐欺といいます。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。
よって、CがBの詐欺を主張して抵当権設定契約を取消すためには、相手方Aが、Bによる当該詐欺の事実を知っていた場合に限り認められるということになります。
この事例では、相手方Aが善意の場合も含めて、詐欺による取消しの主張ができるとしていますので、誤りとなります。
Q44:相手方の欺罔行為により錯誤に陥って贈与の意思表示をした者は、その相手方が贈与を受けた物を善意の第三者に譲渡した後であっても、その意思表示を取り消すことができる?
A44:正しい。
A───────→B───→C(善意の第三者)
(詐欺による譲渡)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができます(民法96条1項)。
この事例では、相手方の欺罔行為で錯誤に陥って、贈与の意思表示をしていますので、取消しをすることができます。
そして、善意の第三者が出てきた後でも、この詐欺による取消し自体はすることができます。
尚、民法96条3項において、詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができないと規定しています。
この規定は、善意の第三者の保護を優先し、取引の安全性を担保するというものですので、詐欺による取消行為自体ができるかどうかとは別の問題になります。
Q45:相手方の欺罔行為により錯誤に陥ってした意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときでも、詐欺を理由として取り消すことができる?
A45:正しい。
要素の錯誤による無効と詐欺による取消しのいずれも主張ができる場合について、どちらを主張することが可能なのか又は両方とも主張できるのかについては、判例では、はっきりとした見解はありません。
通説においては、錯誤無効と詐欺による取消しのいずれを主張しても構わないとしています。
Q46:売買契約における当事者の一方の意思表示につき、錯誤の場合は、誰でも無効を主張することができるが、詐欺の場合は、取消権を行使できる者は限定されている?
A46:誤り。
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とします(民法95条)。
この錯誤無効の主張は、原則として表意者本人またはその承継人のみが主張をすることができ、誰でも主張することができる訳ではありません(通説および判例:最判S40.9.10参照)。
一方の詐欺による取消しは、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り主張することができます(民法120条2項)。
ちなみに、「無効」は原則として誰でも主張できますが、錯誤無効については例外です。
Q47:売買契約における当事者の一方の意思表示につき、錯誤の場合は、当事者の追認によって有効な意思表示に転換する余地はないが、詐欺の場合は、当事者の追認によって確定的に有効な意思表示にすることができる?
A47:誤り。
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じません(民法119条)。
但し、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなします(民法119条但書)。
よって、錯誤無効の場合にも、この但書の規定により、当事者の追認によって有効になることはありえます。
一方、取消しの場合は、追認権者による追認により、確定的に有効なものとすることができます(民法122条)。
Q48:売買契約における当事者の一方の意思表示につき、民法上、錯誤の場合は、無効を主張できる期間の定めはないが、詐欺の場合は、取消権を行使できる期間は定められている?
A48:正しい。
無効については、初めから何らの効力も生じないものですので、主張できる期間の制限はありません。
一方の取消しについては、取消されるまでは一応有効なものとなりますので、いつまでも主張できるとしますと、不安定な状態が続くこととなり、取引の安全性を阻害することになりかねません。
よって民法では、取消権を主張できる期間を定めています。
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、行為の時から20年を経過したときも、同様とします(民法126条)。
Q49:売買契約における当事者の一方の意思表示につき、錯誤の場合は、あらゆる第三者に無効を主張することができるが、詐欺の場合は、すべての第三者に対して取消しを主張することができるわけではない?
A49:正しい。
錯誤無効は、原則として誰に対しても主張することができます。
一方、詐欺による取消しは、取引の安全性を保障する立場から、取消し前の善意の第三者に対抗することができません(民法96条3項)。
Q50:相手方の強迫行為により完全に意思の自由を失って贈与の意思表示をした者は、その意思表示の取消しをしなくても、相手方に対し、贈与した物の返還を請求することができる?
A50:正しい。
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができます(民法96条1項)。
よって、原則として、強迫を受けた者は意思表示の取消しをして、原状回復請求をすることができます。
ただし、この事例においては、相手方の強迫により、完全に意思の自由を失っていますので、このような意思表示は当然に無効であり、民法96条の適用はないと判例(最判S33.7.1)は示しています。
Q51:金銭の借主の強迫行為によって、貸主との間でその金銭債務についての保証契約をした者は、貸主がその強迫の事実を知らなかったときは、保証契約の意思表示を取消すことができない?
A51:誤り。
(貸主)───→(借主)
│ │
│ │強迫
│ ↓
└───→(保証人)
保証契約
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。
民法96条は、1項において、詐欺と強迫による意思表示の両方について規定していますが、2項及び3項については、詐欺についてのみ規定していますので、強迫については反対解釈が成り立ちます。
つまり、第三者による強迫の場合には、相手方がそれを知っているか否かに関わらず、これを取消すことができます。
Q52:甲がその所有する土地を乙に強迫されて売り渡し、更に乙が事情を知らない丙に転売し、それぞれ所有権移転の登記をした場合に、甲は、乙に取消しの意思表示をすれば、丙に対して登記の抹消を求めることができる?
A52:正しい。
(登記) (登記)
甲───→乙───→丙(善意)
(強迫)
詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができません(民法96条3項)。
強迫については、この条文の反対解釈として、善意の第三者にも対抗することができます。
よって、第三者の善意悪意や登記の有無を問わず、強迫による意思表示をした者は、取消しをした上で原状回復請求をすることができます。
ちなみに、詐欺の場合と強迫の場合とでこのように結論が異なるのは、強迫を受けた者の保護の度合いの違いによるものです。
つまり、詐欺の場合は、詐欺を受けた者にも若干の落ち度があると言えるのに対して、強迫の場合にはそのような落ち度は認められないと言えますので、保護する度合いが高くなります。
そこから、善意の第三者が保護を受けるか否かの結論が変わってくることになります。
尚、取消し後の第三者については、民法177条の第三者として位置づけられ、どちらが先に登記をしたかで判断することになります。
つまり、取消しによる強迫を受けた者への原状回復と、取消し後の第三者への移転とが、二重譲渡と同様の関係になるため、民法177条の対抗問題として考える必要があるということです。
(2)譲渡
甲───→乙───→丙
↑ (強迫)
└────┘
(1)取消しによる原状回復
上記の場合、乙を基点として、乙→甲と乙→丙の二重譲渡と同じ状況になりますので、甲と丙のいずれか先に登記を備えた者が、他者に対抗できます。
A53:誤り。
A──→B(強迫)
│
│(債権譲渡、Aへの通知)
│
↓
C(善意)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができます(民法96条1項)。
そして、追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について、当該行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡があったときは、追認をしたものとみなします(法定追認:民法125条1項5号)。
しかし、この法定追認の効果が生じるためには、取消権者であるAがなしたものでなければなりませんので、この事例においては、法定追認の効果は生じません。
よって、Aは債権譲渡の通知を受け取った後でも、取消しをすることができます。
Q54:甲がその所有する土地を乙に騙されて売り渡した後、売り渡しの意思表示を取り消す旨を記載した手紙を出したが、手紙が到達する前に甲が死亡した場合には、取消しの効果は生じない?
A54:誤り。
隔地者、つまり離れた場所にいる者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生じます(到達主義:民法97条1項)。
よって、意思表示を発しても、その通知が相手方に届くまでは、その効力は発しないということになります。
では、この事例のように、通知が相手方に届く前に意思表示をした者(通知を発した者)が死亡してしまった場合はどうなるかといいますと、そのことによって効力が発しなくなることはないとしています。
隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられません(民法97条2項)。
よって、この事例のように、取消しの意思表示を通知した後に、その者が死亡しても、通知が到達した時点で、当該取消しは効力を生じるということになります。
ちなみに、契約の申込みについては、上記民法97条2項の例外規定が定められています。
隔地者に対する契約の申込みの意思表示については、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、当該申込みの効力が生じません(民法525条)。
これは、申込みという行為だけでは意味がなく、その申込に対する相手方の承諾という行為があってはじめて契約が成立する訳ですが、その成立時である申込到達時までに、申込者が反対の意思表示を示していることを知っていた場合や、申込者が死亡していたり、行為能力を失っていたりした場合には、効力を生じさせても意味がないためです。
Q55:未成年者甲の法定代理人乙から甲において土地を買い受けたい旨の申込みを受けた丙が、これを売り渡す旨の意思表示を直接甲に対してした場合には、丙は売買契約の成立を主張することができない?
A55:正しい。
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができません(民法98条の2本文)。
これは、未成年者や成年被後見人には、相手方の意思表示の内容を了知するだけの能力がないとしているためです。
よって、この事例における丙が未成年者甲にした意思表示は、甲に受領能力がないためその効力を生じることはなく、よって売買契約の成立も主張できないということになります。
ちなみに、民法98条の2但書において、法定代理人がその意思表示を知った後は、主張できるとしています。
よって、法定代理人乙が、丙の意思表示を知ったときは、その後は丙は売買契約の成立を主張できます。
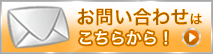 |
| NEXT→民法(総則2)Q&A集 |