遺言Q&A
Q1:遺産分割をしたいのですが、相続人のうちの1人が印鑑を押してくれません。どのようにしたらよいのでしょうか?
A1:遺産分割協議は相続人全員ですることが必要で、一部のものを除いた協議では効力がありません。相続人の内の一人が協議に合意しないということであれば家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
家庭裁判所では各自の主張を調整し、最終的に和解まで進めてくれます。和解に変わる審判が出されることもあります。
Q2:浪費癖のある推定相続人に対する保佐開始の審判の申立を第三者に委託することは、遺言によってすることができる?
A2:誤り。
保佐開始の審判とは、精神上の障害が原因で、事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分である者を保護するため、家庭裁判所が行う審判手続のことです(民法11条)。
よって、浪費癖があるというだけでは、被保佐人(保佐される人)の要件には当てはまりませんので、保佐開始の審判の申し立て自体ができません。よって、遺言によっても当該申立はできないということになります。
Q3:遺言者の嫡出でない子を認知することは遺言によってすることができる?
A3:正しい。
認知とは、非嫡出子について、父又は母との間の法的な親子関係を生じさせる行為をいいます。
そして、認知は、認知をすべき者(父又は母)が、生前に戸籍法の定めるところにより届け出ることによってすることもできますが、遺言によってもすることができます(民法781条1項、民法781条2項)。
これは、認知をすべき者が何らかの理由により、生前には認知ができない場合でも死後に認知をすることで、嫡出子として遺産を相続させたいという意思を認める必要があるためです。
Q4:遺言者が未成年者に対し最後に親権を行う者である場合において、後見人を指定することは、遺言によってすることができる?
A4:正しい。
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができます(民法839条)。
未成年者に対して最後に親権を行う者とは、例えば両親の一方が死亡したため、片親になっている場合のその親などが挙げられます。この場合における親がもし死亡してしまいますと、その子である未成年者には、親権者がいない状況になってしまいます。
未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、一定の者からの請求により、未成年後見人を選任することになります(民法840条)。
しかし、それよりも親権者が、例えばその未成年者をよく知っている第三者に後見人を依頼するなどしたほうが、当該未成年者にとってもよりよい場合がありえます。よって、遺言でこのような指定も認めることができるとしています。
Q5:共同相続人の相続分を定めることを第三者に委託することは、遺言によってすることができる?
A5:正しい。
民法上は、法定相続分の規定を定めてはいますが、被相続人は、この規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができるとしています(民法902条1項)。
例えば、遺言者が、自分では共同相続人の相続分を定めることはしないが、遺産分割協議で揉める可能性が高いので、第三者に相続分を定めることを依頼するというような場合です。
| ■遺言によってのみすることができる事項 | |
| 未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定 | 民法839条、民法848条 |
| 相続分の指定とその委託 | 民法902条 |
| 遺産分割の方法の指定とその委託 | 民法908条前段 |
| 遺産分割の禁止 | 民法908条後段 |
| 遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め | 民法914条 |
| 遺言執行者の指定とその委託 | 民法1006条1項 |
| 遺贈の遺留分減殺の割合の指定 | 民法1034条但書 |
| ■遺言でも生前行為でもすることができる主な事項 | |
| 認知 | 民法781条1項、民法781条2項 |
| 推定相続人の廃除とその取消し | 民法892条、民法893条、民法894条1項、民法894条2項 |
| 祭祀に関する権利の承継者の指定 | 民法897条1項 |
| 特別受益者の相続分に関する指定 | 民法903条 |
| 包括遺贈及び特定遺贈 | 民法964条 |
Q6:遺言は15歳未満の者がした場合であっても、取り消されるまでは有効である?
A6:誤り。
遺言は、民法で定める方式に従わなければ、遺言として法律上の保護を受けることができません(要式性:民法960条)。よって、遺言を書く場合やアドバイスをする場合には、民法の規定に注意しなければならないことになります。
遺言は単独行為であるため、遺言をするためには、行為能力までは求められず、意思能力があれば良いとされています。
民法では、遺言をすることができるのは、満15歳に達した者としています(民法961条)。
この事例では、満15歳未満の者が遺言をしていますので、要式性を満たせず、当該遺言は無効となります。
この「無効」とは、初めから効力が生じないことをいいますので、取り消されるまで有効としている部分が誤りとなります。
Q7:満15歳に達している未成年者は、法定代理人の同意がなくても、死因贈与、遺贈のいずれもすることができる?
A7:誤り。
遺贈とは、遺言によって 遺言者の財産を特定の人に贈与する行為をいいます。遺贈は単独行為ですので、遺言と同じように満15歳に達した者であれば、法定代理人の同意なくして有効にこれをすることができます(民法961条、民法962条参照)。
一方、死因贈与とは、贈与者の死亡により効力が生じる贈与のことをいいます。死因贈与は、贈与者と受贈者との間の契約ですので、これには意思能力だけでは足りず、行為能力が必要となります。
よって、未成年者が死因贈与契約を結ぶためには、法定代理人の同意が必要となります。
A8:誤り。
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効となります(民法966条1項)。
この条文が存在する理由としては、後見人と被後見人の立場上の力関係を考えますと、後見人の方が強いことが明らかであり、後見の計算終了以前の状況では、強制的に当該後見人自身へ利益を誘導させるような遺言をさせる可能性があり、これによって不正行為の隠蔽を図るというような場合もありえるため、これを防ぐというものです。
よって、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合は、このようなことはないと考え、適用を除外しています(民法966条2項)。
Q9:自筆証書による遺言は検認請求手続が遅滞していても、有効である?
A9:誤り。
検認は実体上の効果を判断するものではない(大判大4.1.16)から、遅滞したとしても遺言の効力に影響はありません。
※検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式その他の状態を調査確認し、その偽造・変造を防止し、保存を確実にする目的で行う一種の証拠保全手続きです。その遺言が有効であるかどうかを判断するものではありません。公正証書以外の方式によって作成された遺言書は、すべて検認手続きを受ける必要があります。
Q10:自筆証書遺言が数葉にわたる場合において、契印がないときは、遺言は無効である?
A10:誤り。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。
よって、条文上は、遺言書が複数枚にわたる場合の契印(割印)については規定していません。
判例においては、複数枚にわたる遺言書が、その書式や内容などから1通の遺言書として作成されたものであることが確認できれば、自筆証書遺言として有効であるとしています(最判S36.6.22)。
Q11:自筆証書遺言の日付として年月しか記載されていない場合であっても、他の文書によって作成の日を特定することができるときは、遺言は無効ではない?
A11:誤り。
自筆証書遺言は、遺言書の作成日である年月日が全て明らかになりませんと、無効の扱いとなります。
これは、たとえ他の文書によって当該遺言書の作成日が特定できる場合であっても、同様となります。
Q12:自筆証書遺言の押印が指印でされた場合には、遺言は無効である?
A12:誤り。
民法968条1項では、印を押さなければならないとはしていますが、印の具体的内容についてまでは規定していません。
この押印を必要とする意味としては、遺言者の同一性を明らかにするためのものですので、実印である必要性はなく、三文判(認印)であっても構いませんし、拇印(指印)であっても構わないとされています(最判H元.2.16)。
Q13:自筆証書遺言に氏又は名しか記載されていない場合には、遺言は無効である?
A13:誤り。
氏名を自書させる意味は、遺言者の同一性を明らかにするためのものですので、遺言者が特定できれば、氏のみ、または名のみでも構いません。
Q14:自筆証書遺言を訂正した場合において、訂正箇所に署名がなされていても、その箇所に押印がないときは、遺言は無効である?
A14:誤り。
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません(民法968条2項)。
よって、この方法によらなければ、訂正は効力を生じないことになります。
ただし、この事例にあるように、遺言自体が無効になるわけではありませんので、自筆証書遺言としての要件が整っていれば、遺言は有効なものとして取り扱われることになります。
Q15:自筆証書遺言によって遺言をするには、証人の立会を必要としない?
A15:正しい。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。
自筆証書遺言についての要件はこれだけですので、証人の立会いは、特に要件とはされていません。
ちなみに、証人の立会いが必要とされている普通方式の遺言は、公正証書遺言と秘密証書遺言になります。
Q16:公正証書遺言をするには、証人2人以上の立会いが必要である?
A16:正しい。
公正証書遺言とは、遺言者の口授に基づいて、公証人が作成する遺言のことをいいます。この方法を採ることで、遺言書の原本が公証人役場に保管されることになりますので、紛失や偽造などの恐れは、自筆証書遺言よりも少なくなります。
ただし、遺言書の存在は遺言者以外の人に知られてしまいますし、また、その内容も本人以外の人(公証人や立会人)に知られてしまうという欠点もあります。
この公正証書遺言の方式については、民法969条で以下のように定められています。
(1)証人2人以上の立会いがあること。
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
(3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
(5)公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。
よって、上記(1)より、2人以上の証人の立会いが必要となります。
この証人は、遺言者が真意に基づいて当該遺言をしていることを証明するために立ち会う必要がありますので、実際に公証人とやり取りをする最初から最後まで、引き続いて立ち会う必要があります。
Q17:未成年者及び被保佐人は、遺言の証人又は立会人となることができない?
A17:誤り。
遺言の普通方式では、公正証書遺言や秘密証書遺言で証人の立会いが必要とされています(民法969条、民法970条)。
また、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をす場合には、医師2人以上の立会が必要とされています(民法973条)。
これらの証人及び立会人の欠格事由は、以下の通りです(民法974条)。
(1)未成年者
(2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
よって、未成年者は証人や立会人とはなれませんが、被保佐人は、証人や立会人になることができます。
Q18:盲人であっても、公正証書遺言に立会う証人としての適格を有する?
A18:正しい。
公正証書遺言に立会う証人の欠格事由は、以下の通りです(民法974条)。
(1)未成年者
(2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
よって、盲人であることは欠格事由には該当しませんし、証人として、当該遺言が遺言者の真意に基づいてなされていることを証明することには全く問題ありませんので、証人となることができます。
なお、口のきけない者や耳の聞こえない者の公正証書遺言については、民法でその方法が定められています。
(1)口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、口授に代えなければならない(民法969条の2第1項)。
(2)遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、読み聞かせに代えることができる(民法969条の2第2項)。
Q19:推定相続人の配偶者は、公正証書遺言に立会う証人としての適格性を有しない?
A19:正しい。
推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は、証人又は立会人となることができません(民法974条1項2号)。
これらの者は、遺言に関して利害関係人となりえますので、公正な遺言が作成できない可能性があるためです。よって、推定相続人とその配偶者は、証人・立会人となることができません。
Q20:秘密証書によって遺言をするには、公証人の関与が必要である?
A20:正しい。
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にして、遺言書の存在を公証人に証明してもらう遺言の方法をいいます。
そして民法では以下の方式に従わなければならないと規定しています。
(1)遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと(民法970条1項1号)。
(2)遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること(民法970条1項2号)。
(3)遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること(民法970条1項3号)。
(4)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと(民法970条1項4号)。
よって、民法970条1項3号及び民法970条1項4号の手続きをするために、公証人の関与が必要となります。
Q21:法定の方式を具備していない秘密証書遺言は、遺言として有効となることはない?
A21:誤り。
秘密証書によって遺言をするには、民法970条の方式に従わなければならず、この方式を具備しないものは、秘密証書遺言としては無効となります。
しかし、秘密証書遺言としては無効であっても、他の方式の遺言として有効になる場合があります。
秘密証書による遺言は、秘密証書遺言に定める方式に欠けるものがあっても、民法968条に定める方式(自筆証書遺言の方式)を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有します(民法971条)。これを秘密証書遺言の転換といいます。
よって、秘密証書遺言としては無効でも、自筆証書遺言としての要件を具備していれば、自筆証書遺言として有効となりえますので、誤りとなります。
Q22:パソコンやワープロにより遺言内容を記載し、これに署名捺印した文書は、遺言としての効力を生じない?
A22:誤り。
自筆証書遺言としての要件は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法968条1項)とされています。
よって、パソコンやワープロで文書を作成している以上、自筆証書遺言としては無効となります。
しかし、普通要式の遺言で、自書を求められているのは自筆証書遺言のみであり、公正証書遺言や秘密証書遺言については、他の要件が全て揃っている必要はありますが、パソコンやワープロの文字であっても、それだけで無効とはなりません。
よって、この事例のように全てが無効となるとはいえませんので、誤りとなります。
Q23:遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできない?
A23:正しい。
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません(民法975条)。これを共同遺言の禁止といいます。例えば連名で夫婦が一緒に遺言書を残すこともできません。
これは、複数の人達が一緒に遺言をすることで、遺言の意思に何かしらの影響が出る恐れがあり、遺言者の自由な意思が阻害される恐れがあるためです。
A24:誤り。
停止条件とは、ある条件が成就するまではその効力が生じず(停止)、条件が成就したときから効力を生じるというものです。
この停止条件は、法律行為については原則としてつけることが可能であり、遺言という単独の法律行為についてもつけることができます。
そして、遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる(民法985条2項)としています。
Q25:特定遺贈においては、受遺者は、遺贈が効力を生じた後は、いつでも遺贈の放棄をすることができる?
A25:正しい。
遺贈とは、遺言によって自己の財産を特定の人に贈与するというものです。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
包括遺贈とは、遺贈の目的物を特定せずに、自己の財産の遺贈の割合を示す形で行われるものであり、特定遺贈とは、特定物の遺贈をするものです。
特定遺贈の放棄については、遺言者の死亡後、つまり遺贈の効力が発生した後、いつでも放棄が可能です(民法986条1項)。
ちなみに、包括遺贈の場合には、民法990条で受遺者が相続人と同一の権利義務を有するとされますので、原則として遺言者の死亡を知ったときから3ヵ月以内でないと放棄ができない(民法915条)ことになります。
Q26:特定遺贈を受けた相続人は、その遺贈価額が、全相続財産中に占める割合に応じて相続債務を承継し、相続分の指定を受けた相続人は、指定された割合に応じて相続債務を承継する?
A26:誤り。
相続が発生した場合において、正の財産も負の財産も、各共同相続人がその相続分に応じて被相続人を承継することになります(民法899条)。
よって、特定遺贈を受けた相続人についても、遺贈価額が全相続財産中に占める割合に応じて相続債務を承継する訳ではありません。
一方、相続分の指定ですが、これは民法902条に定められているように、被相続人が遺言で共同相続人の相続分を定めるものです。
この相続分の指定に従って共同相続人が相続すれば、債務も一応はこれに従って承継されることになります。ただし、これをもって債権者に対抗できるかといいますと、通説では対抗できないものとされています。
Q27:遺贈は遺言者の死亡以前に受贈者が死亡したときは、受遺者の相続人に対する遺贈としての効力を有する?
A27:誤り。
遺贈者の死亡以前に受贈者が死亡したときは、その遺贈は効力を生じません(民法994条1項)。
更に、遺贈がその効力を生じないときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する(民法995条)ことになります。
これは、遺贈というものは、遺贈者が特定の人(受遺者)のために、自己の財産の一部を贈与したいという意思に基づくものですので、代襲相続にはなじまないからです。
Q28:不特定物を遺贈の目的とした場合は、物に瑕疵があっても、遺贈義務者は、瑕疵がない物に代えることを要しない?
A28:誤り。
不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければなりません(民法998条2項)。
これは、不特定物である以上、瑕疵のない他の物を提供することが可能であることや、遺贈者は瑕疵のないものを遺贈の目的としていると考えられるからです。
尚、特定物の場合には、たとえその物に瑕疵があっても、その物を引き渡しさえすれば、遺贈義務者は担保責任は負わなくてもいいことになります(民法998条2項の反対解釈)。
Q29:自筆証書遺言による遺贈は、家庭裁判所による遺言の検認がなければ効力を生じない?
A29:誤り。
検認とは、遺言書の保管者が、相続の開始を知った後、遅滞なく、当該遺言書を家庭裁判所に提出し、遺言書の存在を認定してもらう作業です(民法1004条1項)。
この家庭裁判所による検認は、あくまでも遺言書の形式的な確認作業であり、遺言の内容のチェックや、遺言として有効か否かという判断をするためのものではありませんので、この検認手続を経ないというだけで、当該遺言の効力が生じないということはありません。
Q30:遺言書に「私の財産は全部A(相続人でない者)に『まかせる』」旨の記載がありました。これは遺贈と解することができる?
A30:誤り。
判例によると、「まかせる」とは「『まかせる』という言葉は、本来『事の処置などを他のものにゆだねて、自由にさせる。相手の思うままにさせる。』ことを意味するにすぎず、与えるという意味を全く含んでいない」としています。
よって、「まかせる」という文言には「相続させる」のような「与える」趣旨ではないことになります。
遺言の解釈をするに当たっては、遺言書の文言を形式的にのみ判断するものではないとされています。判例では、「遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し」て解釈するとしています。
遺言者の真意を探究して遺言の解釈をするものとはいえ、誰に財産を「与える」のかを明確にする必要があるといえますので、遺言で「与える」趣旨の文言としては、「相続させる」や「遺贈する」を使うのが良いでしょう。
Q31:遺言者は、推定相続人との間で遺言を撤回しない旨を約した後は、遺言を撤回することができない?
A31:誤り。
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。
よって、遺言者は何度でも遺言をすることができますし、遺言の内容の追加や変更もできます。
また、遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができません(民法1026条)。これは、民法1022条の遺言撤回の自由を確保する必要があるために規定されています。
よって、この事例のように、遺言を撤回しないという約束は、無効となりますので、その後も自由に撤回ができることになります。
Q32:公正証書により遺言をした者は、公正証書によらなければ、その遺言を撤回することができない?
A32:誤り。
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。
この条文の「遺言の方式」とは、民法で規定されている遺言の方式の全てを指しますので、撤回しようとしている遺言の方式と同一である必要はありません。
よって、公正証書遺言の撤回を、例えば自筆証書遺言など公正証書遺言以外の方式によってすることも可能です。
Q33:前の遺言と後の遺言とが抵触するときであっても、前の遺言は、抵触をする部分を除いては効力を失わない?
A33:正しい。
前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を取り消したとみなします(民法1023条1項)ので、遺言全体が無効となるわけではありません。したがって前の遺言は抵触する部分を除いては効力を失いません。
Q34:甲が「A家屋を乙に与える」旨の秘密証書遺言をした場合において、甲が故意に遺言書を破棄したときは、これによって遺言を撤回したものとみなされる?
A34:正しい。
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなします(民法1024条)。
これは、故意に破棄するという行為により、遺言者が当該遺言を撤回しようという意思が認められるためです。
A35:正しい。
このような場合において最高裁判所は、「遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、民法1025条ただし書の法意にかんがみ、遺言者の真意を尊重して原遺言の効力の復活を認めるのが相当と解される」として、第1遺言の復活を認めています(最判平9.11.13)。
Q36:遺言を撤回した後、その撤回の行為を強迫を理由に撤回しても、遺言の効力は回復しない?
A36:誤り。
撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しません。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りではありません(民法1025条)。
原則として、いったん撤回した遺言は、その撤回を取消しても、復活することはありませんので、改めて遺言をし直す必要があります。
しかし、遺言を撤回した行為自体が詐欺・強迫に基づく場合には、撤回行為の取消により、その効力が回復することになります。
ちなみに、民法1025条但書の回復の例外は、詐欺・強迫のみです。行為能力の制限を理由とする回復はありませんので、注意が必要です。
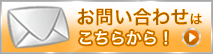 |
| NEXT→相続Q&A集 |