民法(総則2)Q&A集
A56:誤り。
代理とは、本人に代理権を付与された代理人が、その者(本人)のために意思表示をし、またはこれを受けることによって、本人が直接その法律行為の効果を取得する制度です。
この代理制度があることで、本人は代理人を活用し、その活動範囲を拡張することができることになります。
乙(本人)
|
|(代理契約)
|
甲(成年被後見人)────→丙(第三者)
代理人は、行為能力者でなければならないかといいますと、民法では、行為能力者であることを要しないとしています(民法102条)。
これは、代理人がした行為の効果は本人に帰属しますので、たとえ代理人が制限行為能力者であっても、この者には不利益が及ぶことがなく、この者を保護する必要がないためです。
また、本人も、制限行為能力者であることを知った上で代理権を付与していますので、何ら問題がないことになります。
よって、この事例における甲の意思表示は、本人乙に帰属しますので、有効となり、その後は取消すことができません。
A57:正しい。
乙(本人)
|
|(代理契約、委任契約)
|
甲(未成年者)─────→丙(第三者)
この事例で問われているのは、甲乙間の代理契約の成立についてです。
そうしますと、未成年者が法定代理人の同意を得ないでできる法律行為は、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為だけですので、この委任契約については、法定代理人の同意が必要であるということになります。
よって、甲は、甲乙間の契約について、取消すことができます。
Q58:代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした場合であっても、相手方がその本人のためにすることを知っていたときには、その意思表示は、直接本人に対して効力を生じる?
A58:正しい。
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生じます(民法99条1項)。
一方、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示については、原則として、代理人が自己のためにしたものとみなします(民法100条本文)。
これは、代理人と取引をする相手方は、本人の存在を知らない場合には、取引の効果がその本人に帰属してしまうと、不測の損害を被る恐れがあるためで、この相手方を保護するための規定です。
当該代理人が本人のためにすることを相手方が知っていれば、不測の損害を被る恐れがないので、保護する必要はないということになります。
つまり、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接にその効力を生ずることとなります(民法100条但書)。
A59:正しい。
甲(本人)
|
|
|
乙(代理人)────────丙
売買契約(家屋)
※丙の詐欺につき、乙は悪意、甲は善意
意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとします(民法101条1項)。
これは、代理人の行為の帰属は本人になりますが、意思表示をしているのはあくまでも代理人であり、代理人の善意悪意で判断すべきものだからです。
この事例においては、代理人乙は、丙の詐欺行為について知っており、錯誤に陥っていません。
よって、本人甲は、詐欺を理由として当該契約を取消すことはできません。
Q60:Aの代理人Bの代理行為が、相手方Cとの通謀虚偽表示に基づくものであった場合において、Aがそのことを知らなかったときは、Cは、Aに対しその行為について無効の主張をすることができない?
A60:誤り。
A(本人・善意)
|
|
|
B(代理人)──────→C(相手方)
通謀虚偽表示
通謀虚偽表示とは、相手方と共謀して虚実の意思表示をすることをいい、この虚偽の意思表示は、無効となります(民法94条1項)。
そして、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができません(民法94条2項)。
この事例では、代理人と相手方とが通謀していますが、意思表示の効力が意思の不存在によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする(民法101条1項)と規定されていますので、この代理行為は無効となります。
では、通謀の当事者Cは、Aに対して無効を主張できるかといいますと、判例では主張できるとしています。
これは、Aが民法94条2項の「善意の第三者」には該当しないためです。
A61:正しい。
A(本人・悪意)
|
|
|
B(代理人・善意無過失)←───C(相手方・無権利者)
動産の即時取得とは、動産の取引において、当該動産を占有している者を信頼して取引関係に入った者は、その占有者が無権利者であっても、その動産について権利を取得するという制度です(民法192条参照)。
代理行為の瑕疵について、条文では、代理人が特定の法律行為をすることを委託された場合において、本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない(民法101条2項)と定めています。
つまり、原則として、意思表示の効力がある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする(民法101条1項)のですが、そのことを悪意又は有過失の本人が主張することは、信義則上も問題があるということです。
A62:正しい。
B(本人)
|
A(任意代理人)
|
C(復代理人)
復代理人とは、代理人が自分の名において、自分以外の者を本人の代理人として選任した者をいい、代理人自身の代理権の範囲内で、本人のために代理行為を行います。
つまり、復代理人は、第三者から見ますと、代理人と全く同じであり、本人のためにすることを示した上で代理行為をすることになります。
よって、代理人は、行為能力者であることを要しない(民法102条)という規定が、復代理人の場合にも当てはまることになります。
Q63:委任による代理人は本人が特に反対の意思を表示しない限り、復代理人を選任することができる?
A63:誤り。
代理人には、任意代理人と法定代理人の2種類があります。
任意代理人とは、本人の信頼に基づき、本人の意思によって生じる代理権を有する者であり、法定代理人とは、法律の規定に基づいて生じる代理権を有する者を指します。
委任による代理人は、法定代理人と異なり、本人の信任に基づくものですし、また、いつでも辞任することができますので、原則として復任権は認められておらず、例外として、本人の許諾がある場合またはやむを得ない事由がある場合のみ、認められています(民法104条)。
ちなみに、法定代理人は、法律上定められた者がその任にあたりますので、辞任は容易ではありませんし、その権限も広範囲に渡りますので、いつでも自由に復代理人を選任することができます。
Q64:委任による代理人の復代理に関し、代理人は、本人の許諾を得て復代理人を選任したときは、その選任及び監督について本人に対し責任を負う?
A64:正しい。
委任による代理人は、復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負います(民法105条1項)。
代理人は、復代理人を選任するにあたり、代理行為をきちんと遂行できる人を選ぶ責任を負うのは、当然のことといえます。
また代理人は、復代理人を選任した後も、代理人としての地位をそのまま継続しますので、復代理人の監督義務も生じます。
なお、法定代理人の場合には、法定代理人が自己の責任で復代理人を選任することができます(無過失責任:民法106条前段)。
そして、やむを得ない事由により復代理人を選任する場合には、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負います(民法106条後段)。
A65:誤り。
任意代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、当該復代理人の選任及び監督についての責任を負いません(民法105条2項本文)。
これは、本人が指名した者である以上、本人が責任を取ればいいのですから、当然のことであります。
ただし、代理人は、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、責任を負うことになります(民法105条2項但書)。
Q66:復代理人は、代理行為をするに当たっては、本人のためにすることを示すほか、自己を選任した代理人の名を示すことを要する?
A66:誤り。
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表します(民法107条1項)。
よって、復代理人はあくまでも本人の代理人ですから、代理行為をなすにあたり、本人のためにすることを示す必要はありますが、代理人の名を示す必要はありません(民法99条1項参照)。
Q67:復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても、消滅しない?
A67:誤り。
復代理人は、本人の代理人としてその代理権の範囲内で代理行為をしますので、代理人に選任されているとはいえ、その行動は別個独立しているようにも見えます。
しかし、復代理人の代理権は、代理人の代理権に基づくものであり、代理人の代理権の範囲内でのみ存在できるものです。
よって、代理人の代理権が消滅すれば、復代理人の代理権も消滅することになります。
A68:正しい。
甲(本人)
|
|
|
乙(代理人)───────→丙
権限外の代理行為
本来、代理人に代理権がない場合には、その代理人がする行為は、本人には非がないため、本人が追認しない以上は無効となります(民法113条1項)。
これは本人の立場に立てば当然のことですが、無効になってしまうことで、代理人と取引をした相手が困ってしまうことになります。勿論、無権代理人に責任を追及することは可能です。
そこで、一定の理由があり、相手方としては代理権があることを信じるのにやむを得ないであろうと思われる場合は、表見代理として、これらの相手方(第三者)を保護し、取引の安全を図ろうとしています。
この表見代理には、次の3つの種類があります。
(1)代理権授与の表示による表見代理(民法109条)
(2)権限外の行為の表見代理(民法110条)
(3)代理権消滅後の表見代理(民法112条)
この事例は、(2)の「権限外の行為の表見代理」に該当する可能性があります。
代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについては、本人はその責任を負います(民法110条)。
この「権限外の行為の表見代理」が成立する要件としては、次のものが挙げられます。
●基本代理権の存在=無権代理人が基本代理権を有していること。
●基本代理権の権限以外の事項につき、代理行為がなされること。
●相手方が代理権があるものと誤信し、かつその誤信に正当の理由があること。つまり、善意・無過失であること。
この事例では、相手方丙に正当な理由があるとしていますので、上記の要件をすべて満たし、表見代理が成立します。
よって、当該売買契約は成立しますので、本人甲は、当該売買代金の請求を拒むことはできません。
A69:正しい。
甲(本人)
|
|
|
乙(代理人)───────→丙
権限外の代理行為
無権代理の場合には、相手方は本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます(民法114条)。
そして、無権代理については、原則として本人は、追認を拒絶することができます(民法113条1項)。
しかし、表見代理が成立する場合については、本人よりも相手方の保護(取引の安全の確保)を優先しますので、本人は拒絶することができません。
この事例においても、相手方丙は、代理人乙の代理権が「権限外の行為の表見代理」に該当することを理由として、表見代理の成立の主張をすることができます。
A70:正しい。
夫(本人)
|
|
|
妻(無権代理人)───────→第三者
無権代理行為(日常の家事に関しない法律行為)
日常の家事に関しては、民法上では、夫婦で連帯責任を負う旨を定めています。
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負います(民法761条)。
しかし、この事例においては、日常家事に関する法律行為ではないため、民法761条の要件は満たしません。
判例では、夫婦の一方が日常の家事に関する代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合においては、民法110条の表見代理を認めてしまうと夫婦の財産的独立を損なう恐れがあるため、夫婦の一方が他の一方に対して何らかの代理権を与えていない以上は、相手方が日常の家事に属すると信ずるにつき正当の理由がある場合のみ、民法110条の表見代理の成立を類推適用することとしました(最判S44.12.18)。
Q71:代理人の代理権が消滅した後にその者がした無権代理行為につき、民法112条の表見代理が成立するためには、代理権が消滅する前に、その代理人が当該本人を代理して相手方と取引行為をしたことがあることを要する?
A71:誤り。
表見代理は3種類あります。
(1)代理権授与の表示による表見代理(民法109条)
(2)権限外の行為の表見代理(民法110条)
(3)代理権消滅後の表見代理(民法112条)
この事例で問われているのは、(3)の「代理権消滅後の表見代理」です。
「代理権消滅後の表見代理」の表見代理が成立する要件は、以下の通りです。
●かつて存在していた代理権が、代理行為当時には消滅していたこと。
●代理人が、かつて存在していた代理権の範囲内で行為をすること。
●相手方が、代理権の消滅につき、善意かつ無過失であること。
この事例では、「代理権消滅後の表見代理」の表見代理の成立のためには、代理権消滅前の取引行為が必要とされていますが、取引行為のない相手方も保護する必要がありますので、誤りとなります。
Q72:無権代理人がした契約の追認に関し、本人は、無権代理人が本人の利益を図る意思で契約をした場合に限り、契約を追認することができる?
A72:誤り。
無権代理行為とは、その名のとおり代理権を持たずに代理人と称して法律行為を行うわけですから、表見代理が成立する例外を除いて、本人に責任を負わせるべきではありません。
よって、本人は追認をしない間は、当該行為の取消しをすることができます。
つまり、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じません(民法113条1項)。
さて、この追認ですが、本人自身が無権代理人の法律行為の帰属を認める分には、何ら問題がありませんし、相手方にとっても利益となりますので、自由にすることができます。
よって、無権代理人が本人の利益を図る意思で契約をした場合に限らず、追認をすることができます。
Q73:無権代理人の行為が表見代理とならない場合において、本人は、無権代理人に対して追認する旨の意思表示をしたときは、相手方がそのことを知らなくても、相手方に対して追認の効果を主張することができる?
A73:誤り。
無権代理行為に対する本人の追認の意思表示は、無権代理人に対してでも、相手方に対してでも、どちらでも構いません。
ただし、無権代理人に対してした場合は、相手方に伝わり、その事実の認識がなされるまでは、相手方に対抗することができません。
追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができません。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りではありません(民法113条2項)。
A74:誤り。
甲(本人)
|
|
|
乙(代理人)───────→丙(悪意)
無権代理行為
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じません(民法113条1項)。
よって、本人は、無権代理行為に対して、追認又は拒絶をすることで保護されることになりますが、一方の相手方にとっては、早くいずれかの意思表示をしてもらいませんと、いつまでも不安定な立場が続くことになってしまいます。
そこで、民法では、相手方の保護のために、本人に対して催告をすることができるとしています。
無権代理行為において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます(民法114条前段)。
この催告権は、相手方がいつまでも不安定な立場に置かれることのないようにするためのものですので、当該相手方は、善意の者だけでなく、代理人に代理権がないことを知っていた場合(悪意)でも、行使することができます。
Q75:無権代理人がした契約の追認に関し、相手方が本人に対して相当の期間を定めて契約を追認するか否かを催告したが、応答のないままその期間が経過した場合、本人は、契約を追認したものとみなされる?
A75:誤り。
無権代理人がした契約の相手方は、相当の期間を定めて、本人に対して追認をするかどうかを確答するべき旨の催告をすることができます(民法114条前段)。
では、その期間に本人が確答をなさなかった場合はどうなるのかといいますと、無権代理行為については、元々本人には非がない訳ですので、これだけで本人が追認したものとみなしてしまうのは、酷といえます。
よって、本人の確答のない場合は、追認を拒絶したものとみなします(民法114条後段)。
A76:誤り。
B(本人)
|
|
|
A(無権代理人)────→C(相手方)
本人は、無権代理行為について追認又は拒絶をすることができます(民法113条)。
本人が追認をした場合の効力の発生時期は、契約時まで遡及します。
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生じます(民法116条本文)。
これは、追認をした本人としては、無権代理人が契約をした時点から、自己のためにしたものとして当該行為を帰属させる意思であると考えるのが一般的ですし、また、相手方にとっても、契約当初から効力が発生することは、当初の期待どおりとなるからです。
ただし、遡及をすることで第三者の権利を侵害してしまいますと、当該第三者に予測できない不利益を被らせてしまいますので、第三者に対しては、遡及の制限が定められています(民法116条但書)。
A77:誤り。
甲(本人)
|
|
|
乙(無権代理人)───────────→丙(相手方)
無権代理行為(本人追認)
本人甲が乙の無権代理行為を追認したことで、当該契約の効果は本人に帰属することになります。
そうしますと、相手方は、本人に対して、直接売買代金の請求をすることになります。
この事例において、相手方丙が無権代理人乙へ売買代金の支払いを請求するというのは、本人が当該無権代理行為を拒絶した場合に、無権代理人が負う責任のことを指しています。
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負います(民法117条1項)。
この無権代理人の責任が生じる要件としては、次のようになります。
(1)代理人が代理権を証明できないこと
(2)本人の追認がないこと
(3)相手方が、(自称代理人に代理権がないことにつき)善意無過失であること
(4)相手方が、民法115条の取消権を行使しないこと
(5)無権代理人が行為能力者であること
この事例では、本人が追認をしていますので、無権代理人が相手方に対して責任を負うことはありません。
よって、相手方は、無権代理人に対して履行の請求、つまり売買代金の支払請求をすることはできません。
A78:誤り。
B(本人)
|
|
|
A(無権代理人)────→C(相手方)
←責任追及
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(無権代理人の責任:民法117条1項)ことになります。
よって、無権代理行為を行った無権代理人は、本人の追認がない以上、履行又は損害賠償の責任を負う必要があります。
では、当該無権代理行為が表見代理の要件に該当する場合において、無権代理人がその主張をすることができるのかといいますと、判例(最判S62.7.7)ではこれを認めていません。
このような抗弁を認めてしまいますと、無権代理人の言い逃れを認めてしまうことになりかねないためです。
A79:正しい。
B(本人)
|
|
|
A(無権代理人)─────→C(相手方)
←責任追及(損害賠償請求)
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(無権代理人の責任:民法117条1項)ことになります。
よって、相手方が損害賠償の責任を求めてきた場合には、無権代理人はその責を負わなければなりません。
無権代理人に請求することができる損害賠償額は、信頼利益(契約締結のために要した費用)だけでなく、履行利益(契約が履行されたら得られるはずであった利益)も含めた範囲内で請求することができると判例は示しています。
Q80:Aが被保佐人Bに金銭を貸し付け、その後にBについての保佐開始の審判が取り消された場合において、BがAに対して新たに担保を提供したときは、追認をしたものとみなされる?
A80:正しい。
取消しの原因となっていた状況が消滅し、追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなします。ただし、異議をとどめたときは、この限りではありません(法定追認:民法125条)。
(1)全部又は一部の履行
(2)履行の請求
(3)更改
(4)担保の供与
(5)取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
(6)強制執行
法定追認とは、追認できる者が、取り消しうべき行為について、一定の行為をした場合に、法律上、追認をしたものとみなすものですので、その後は、原則として取り消しができなくなります。
この事例においては、被保佐人ではなくなってから、つまり追認できるようになった後に債権者に対して担保の提供をしていますので、上記(4)の「担保の供与」に該当することになり、法定追認が成立します。
Q81:Aの詐欺により、BがAから旧式の乗用自動車を高額で買い受けた場合において、Bが詐欺であることに気づかないまま、その自動車を他人に譲渡したときは、追認をしたものとみなされる?
A81:誤り。
相手方の詐欺により乗用車を購入したBは、詐欺による取り消しをすることができます(民法96条1項)。
では、この事例のように、詐欺であることに気づかないまま、第三者に当該乗用車を譲渡した場合に、これが民法125条1項5号の法定追認に該当するのかどうかが問題となります。
この法定追認を適用するための前提としては、民法124条に追認の要件が定められています。
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じません(民法124条1項)。
取り消しの原因である状況が止んだ後、つまりこの事例においては、詐欺の事実に気づいた後でなければ、追認自体が無効となり、これは法定追認にも当てはまります。
よって、この事例では、第三者への譲渡行為が追認とみなされることはありません。
Q82:条件に関する次のアからオまでの事例の内、正しいものはどれか。
ア.停止条件又は解除条件が付された場合には、条件成就の効果は、特約がない限り条件成就の時に発生し、遡及しない?
イ.不法な行為をしないことをもって停止条件又は解除条件とする法律行為は、無効である?
ウ.債務者の意思のみにより停止条件が成就するような法律行為は、無効である?
エ.社会通念上、実現が不可能な停止条件を付した法律行為は、無効である?
オ.法律行為の当時、既に条件が成就していた場合において、その条件が解除条件であるときは、その法律行為は無効である?
A82:全て正しい。
条件とは、法律行為の効力の発生や消滅を将来の成否が未定の事実にかからせる旨の特約のことをいいます。
法律行為に条件をつけることは原則有効ですが、以下の例外もあります。
(1)条件に親しまない行為→例:婚姻や縁組、相手の承認・放棄
(2)単独行為→例:解除、取消、追認
(3)不法行為
(4)純粋随意条件(債務者の意思のみにかかる停止条件付法律行為)→例:気が向いたら債務を支払う。
尚、条件のうちの「停止条件」と「解除条件」については、成就しますと、次のような効果があります。
・停止条件→法律行為は効力を生じる。
・解除条件→法律行為は効力を失う。原則として遡及しない。
※条件には、この他にも「既成条件」「不能条件」があります。
ア.
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じます(民法127条1項)。
解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失います(民法127条2項)。
よって、原則として、いずれも条件成就のときに発生し、遡及しません。
ただし、特約として、当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従います(民法127条3項)。
イ.
不法な条件を付した法律行為は、無効とします。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とします(民法132条)。
不法条件をつけることや、不法行為をしないことを条件とする法律行為が無効とされるのは、条件が付されることによって、法律行為全体が不法性・反社会性を帯びるためです。
ウ.
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とします(民法134条)。
例えば、「気が向いたら債務を支払う」という条件は、当該債務者が債務を支払う意思があるかどうかが不明であり、結局、当事者を法律的に拘束する意味を持たないと解されるので、無効とされています。
ちなみに、停止条件の成就が、債権者の意思にのみかかる場合は有効とされています(純粋随意停止条件付法律行為)。
エ.
不能の停止条件を付した法律行為は、無効とします(民法133条1項)。
不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とします(民法133条2項)。
不能の停止条件をつけた法律行為は、いつまでも停止したままですので、条件が成就されることがない以上、無効となりますし、逆に、不能の解除条件を付した法律行為は、いつまでも解除となる条件が成就しない以上、法律行為の効力が消滅することがないためです。
オ.
条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とします(既成条件:民法131条1項)。
A83:正しい。
時効の効力は、その起算日にさかのぼります(民法144条)。
時効とは、一定の事実状態が継続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度で、この時効には、以下の2種類があります。
(1)取得時効→占有(準占有)という事実状態を根拠として、権利が取得されるもの
(2)消滅時効→権利不行使の事実状態を根拠として、権利が消滅するもの
時効の起算点は、以下のとおりです。
(1)取得時効の起算点→占有を開始したとき
(2)消滅時効の起算点→権利行使について法律上の障害がなくなったとき(民法166条1項)
時効が完成しますと、各々の起算点まで遡及することになります。
Q84:時効は、当事者が援用しない限り、これによって裁判をすることはできない?
A84:正しい。
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができません(民法145条)。
時効の援用とは、時効の利益を享受する旨の意思表示のことをいいます。
時効の援用が必要な理由としては、時効制度が継続した事実状態を尊重する一方で、時効の利益を強要することはさせずに、個人の意思も尊重し、両方の調和を図る考えによるものです。
Q85:主たる債務について消滅時効が完成した場合には、主たる債務者が時効の援用をしないときでも、その連帯保証人は、主たる債務につき時効の援用をすることができる?
A85:正しい。
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができません(民法145条)。
この条文の「当事者」の範囲は、時効により直接に利益を受ける者及びその承継人のみと判例(最判S42.10.27)では示しています。
時効の援用権者の具体例としては、以下のような者が挙げられます。
・取得時効→転得者、賃借権者、地上権者等
・消滅時効→連帯債務者、保証人、連帯保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者、詐害行為の受益者等
連帯保証人については、債務者の主たる債務の消滅時効が完成すれば、連帯保証債務の付従性により、連帯保証債務も消滅し、その責を免れますので、直接利益を受ける者に該当します。
よって、連帯保証人は、主たる債務者が消滅時効を援用しない場合であっても、当該消滅時効を援用することができます。
Q86:債務者は、消滅時効完成前に時効の利益を放棄することができない?
A86:正しい。
時効の利益は、あらかじめ放棄することができません(民法146条)。
これは、あらかじめ放棄することができることとしてしまいますと、債権者が債務者にあらかじめ消滅時効の放棄を強要する可能性があり、債務者にとって不利益を被る可能性があるためです。
Q87:主たる債務者が債務を承認した場合でも、その連帯保証人については、時効中断の効力が及ばない?
A87:誤り。
時効は、次に掲げる事由によって中断します(時効の法定中断事由:民法147条)。
(1)請求(民法147条1項1号)
(2)差押え、仮差押え又は仮処分(民法147条1項2号)
(3)承認(民法147条1項3号)
上記各号の事実がありますと、法律上、時効中断があったこととみなされます。
この事例における債務承認は、この法定中断に該当しますので、債務者の持つ主たる債務については時効中断します。
では、連帯保証債務についてはどうなるのでしょうか。
原則として、時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有します(民法148条:相対効)。
しかし、保証債務の場合にもこの原則を貫きますと、先に保証債務のみが消滅時効にかかる恐れがあり、債権者にとっては不利益となることになるため、民法の債権編の条文で例外が定められています。
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生じます(民法457条1項)。
よって、連帯保証人に対しても時効中断の効力が及ぶことになります。
Q88:債権者が債務者に対し債権の支払請求訴訟を提起した場合でも、訴えが却下されたときは、時効中断の効力を生じない?
A88:正しい。
債権の支払請求訴訟の提起は、法定中断事由(民法147条)のうちの「請求」(民法147条1項1号)に該当します。
よって、一旦は時効が中断するのですが、当該訴えが却下された場合には、この時効中断の効力が失われてしまうこととなります。
つまり、裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じません(民法149条)。
これは、裁判で訴えの却下が確定したり、訴えた者(原告)が当該訴えを取り下げた場合には、従前の状態(訴え提起前の状態)が継続する訳ですので、時効の中断もなかったものとして扱うべきものだからです。
Q89:債務者が消滅時効完成後に債務を承認した場合には、時効が完成したことを知らなかったときでも、その時効を援用することはできない?
A89:正しい。
債務者の債務承認は、時効の中断理由に当たります(民法147条1項3号)。
判例では、消滅時効が完成していて、債務者自身がその事実を知らずに承認してしまった場合でも、信義則上、もはや時効を援用することは許されないと示しています(最判S41.4.20)。
Q90:時効の利益を受ける者が時効によって権利を失う者に対してする承認は、時効中断事由であり、例えば、債務者である銀行が銀行内の帳簿に利息の元金組入れの記載をした場合が、これに該当する?
A90:誤り。
承認は、時効の中断事由に該当します(民法147条1項3号)。
この承認とは、時効の利益を受ける者が、権利者に対して権利の存在を認めるものですので、相手方に対する明示または黙示の表示が必要とされています。
よって、この事例のように、銀行が銀行内の帳簿に利息の元本組入れの記載をしただけでは債務を承認したことにはならないと、判例は示しています。
A91:正しい。
催告とは、相手方に対して、義務の履行を求める意思の通知であり、例えば債権者が債務者に対して弁済を促す内容証明郵便を出すような行為を指します。
しかし、この催告は暫定的な中断効しかありませんので、条文上、6箇月以内に次の行為をしなければ、時効中断の効力を生じないとしています。
催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じません(民法153条)。
Q92:被保佐人が保佐人の同意を得ないで債務の承認をした場合であっても、時効の中断の効力を生ずる?
A92:正しい。
被保佐人は制限行為能力者ですので、ある一定の法律行為(民法13条1項各号参照)については、保佐人の同意を要することになります。
ただし、時効中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力または権限があることを要しない(民法156条)としています。
判例においても、保佐人の同意を得ずに、時効完成前に被保佐人が債務の承認をした事例について、時効中断の効力を認めています。
Q93:裁判上の請求により中断した時効は、その裁判が確定したときから、再び進行を始める?
A93:正しい。
裁判上の請求により中断した時効は、当該裁判の確定により、当該訴えの提起の時点で、一旦、時効中断の効力が発生します。
しかし、中断した時効は、中断事由が終了しますと、中断事由が終了した時から新たに進行することになります(民法157条1項)。
A94:正しい。
中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始めます(民法157条1項)。
よって、時効中断するまでの期間については、完全に消滅することになります。
一方の時効の停止は、時効の完成の一時的な猶予のことであり、停止事由が生じても、過去の時効期間の経過が無意味にならない点が、時効中断と異なる点です。
時効の停止事由は、次の5種類があります。
(1)時効完成6箇月内の時期に、未成年者又は成年被後見人が法定代理人を有していない場合(民法158条1項)
(2)未成年者又は成年被後見人が、その財産を管理する法定代理人に対して権利を有する場合(民法158条2項)
(3)夫婦の一方が、他方に対して権利を有する場合(民法159条)
(4)相続財産に関し、相続財産の管理者が不在の場合(民法160条)
(5)天災等により時効の中断手続が取れない場合(民法161条)
Q95:夫婦の一方が他の一方に対して有する債権の消滅時効は、婚姻解消の時から進行を始める?
A95:誤り。
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行します(民法166条1項)。
この事例のように夫婦の一方が他方に対して有する債権であっても、権利を行使することができる時から消滅時効は進行し始めます。
よって、婚姻解消前でも権利を行使することが可能となれば、その時点から消滅時効の進行が開始します。
Q96:10年より短い消滅時効期間のある債権でも、その債権が裁判上の和解により確定している場合には、その消滅時効期間は、10年に延長される?
A96:正しい。
消滅時効の期間は、原則として以下の通りです。
・債権→10年間
・債権または所有権でない財産権→20年間
10年より短い時効期間の定めを、短期消滅時効といいます(民法169条〜民法174条参照)。
これらの短期消滅時効のあるものについて、判決で確定した場合の消滅時効期間の特例として、条文に定めがあります。
確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とします。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とします(民法174条の2第1項)。
この理由としては、確定判決や確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、当該判決等によって債権の存在が公に確認され、強い証拠力が与えられるため、短期消滅時効を認める必要がないからです。
ちなみに、消滅時効にかからない権利は、以下の通りです。
1.所有権
2.所有権に基づく請求権(例:物権的請求権、登記請求権、共有分割請求権)
3.相隣権
4.占有権、留置権、先取特権
5.質権、抵当権
Q97:債務不履行によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時から進行する?
A97:正しい。
債務不履行によって生じる損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、本来の債務の履行を請求することができる時になります。
この理由としては、損害賠償請求権というものが、本来の債権の履行請求権の拡張的なものであり、履行請求権と同一のものと考えられるためです。
Q98:契約の解除による原状回復請求権は、解除によって新たに発生するものであるから、その消滅時効は、解除の時から進行する?
A98:正しい。
契約の解除によって発生する原状回復請求権の消滅時効は、契約解除の時から開始します。
原状回復請求権は、解除権を行使することによって初めて発生する権利だからです。
Q99:割賦払債務について、債務者が割賦金の支払を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がある場合には、残債務全額についての消滅時効は、債務者が割賦金の支払を怠った時から進行する?
A99:誤り。
この事例のような約定は有効であり、当該約定がある場合には、債務者が割賦金の支払を怠ったときに、残債務全額の弁済請求をすることができます。
ただし、当該約定がある場合でも、原則としては、各々の割賦金債務についての消滅時効は、各々の約定の弁済期毎に進行します。
そして、債権者が、残債務全額の弁済を求める意思表示をした場合に限り、その請求のときから、残債務全額についての消滅時効が進行を開始することになります(最判S42.6.23)。
Q100:債権者不確知を原因とする弁済供託をした場合には、供託者が供託金取戻請求権を行使する法律上の障害は、供託の時から存在しないから、その消滅時効は、供託の時から進行する?
A100:誤り。
債権者がどこにいるのか分からない又は誰なのか分からない場合等、債務者が弁済をしたくてもできない場合は、供託所に供託することができ、これによって、債務不履行の責から免れることができます(民法494条後段)。
このような弁済供託において、供託した債務者は、供託する必要のあった元々の債務が時効消滅した場合等は、当該供託金を取戻すことができます。
このような弁済供託における供託物の取戻請求権の消滅時効の起算点は、上記の事例のように、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時からとなります(最判H13.11.27)。
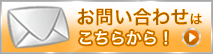 |
| NEXT→民法(物権)Q&A集 |